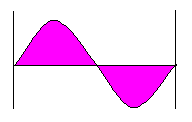
アナログ信号とデジタル信号
アナログ信号は連続した波。
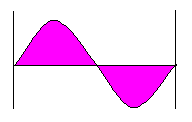
マイクから取り出したアナログ信号には、必要な音と、不要な音(雑音)が混じっている。
例えば歌と伴奏を録音する時、歌そのもの、伴奏そのもの、以外の雑音が混じっている。
録音する時にはレコードでもテープでも、摩擦が生じる。
この摩擦で雑音が更に加わる。再生時には、また摩擦で雑音が加わる。
歌そのもの、伴奏そのものだけで雑音のない音にしたい。
そこで、デジタル信号に変換する技術が開発された。
デジタル信号はデータの集まり。アナログ信号の波に近い波をデータで作っている。

不要な音は切り捨てることができる。
これを圧縮といい、mp2、mp3、mp4など様々な方法がある。
録音、再生時にも摩擦がないので、雑音が加わらない。
こうして出来上がった音は極力雑音が少ない音になる。
歌や伴奏の音が取り出せて、雑音が少ない。
これを追求していくと確かに本物に近い音になるが物足りなさを感じる。
人は音を聞くとき、音として意識できる周波数(可聴音)と、意識できない周波数の
両方を聞いている。
本物の音には意識できない周波数が含まれている。
アナログ録音にはそれが含まれ、デジタル録音にはそれがない、ということに気付く。
そこで、デジタル録音でも可聴音以外を含んで、
より本物に近い音が追及されるようになった。
音の保存の仕方(記録の仕方、入れ物)は色々あるけれど、
元の音は空気を伝わって来て、アナログ信号やデジタル信号に変換されて保存。
再生される時は空気を伝わって耳に届く、
というのは同じ。
パソコンが扱うデータ
パソコン(PC)はデジタルデータを扱う機械。
マイク端子から入ってくる音はアナログ信号だが、
それをデジタル信号に変えて、データとして扱う。
CDなどの音楽データはデジタル信号なのでそのまま処理される。
そして、スピーカーから音を出す時には、デジタル信号をアナログ信号に変えて、
空気を振動させて聞こえる音になる。
ちなみに、
PCの電源ボタンにはリンゴのマークがデザインされている。
これは0と1を表わしていて、デジタルという意味。
録音・編集作業の種類
音の信号がアナログ信号か、デジタル信号か、という分け方の他に、
音の扱い方(編集の仕方)で、アナログ、デジタル、という言葉を使います。
アナログ的な録音
ピアノ、ギター、歌、それぞれの担当者が揃って、
生演奏をして歌って録音。これが元々の録音作業。
ライブコンサートの録音がこれ。一発勝負なので、間違ってもやり直しがきかない。
やり直しを考えて、それぞれの担当の音だけを録音しておいて、
それを合わせていくやり方もできる。
例えば伴奏だけをカセットテープなどに録音しておいて、
それに合わせて歌を録音する。
この時、音の重ね方(音の編集方法)は機械的(アナログ的)。
録音された音を入れる入れ物がレコード、カセットテープ、CDの違いはあっても、
録音の仕方はアナログ的録音。
一昔前の録音方法がこれ。
デジタル的な録音
録音・編集する機材がパソコンなど、デジタル信号を扱うものであれば、
マイク録音で入ってくる音がアナログ信号でもデジタル信号に変えて扱う。
デジタル録音処理を説明すると、
マイクから、ピアノ、ギター、歌をそれぞれ録音。音をデジタルデータに変える。
他にデジタルデータとしてドラムの音色をいくつかと、
それにリズムのデータを加えて用意する。
ピアノ、ギター、歌、それとドラムのデータを合成して、音の位置を調整する。
すると、その場にドラムを叩く人がいなくても、
ピアノ、ギター、歌に加えて、ドラムの音が入った音楽としてできあがる。
ピアノ、ギターの音もデータとして用意しておいて、それぞれの音の位置を調整する。
これに歌だけを重ねればアナログ録音と同じ音を録音できる。
これがデジタル録音。
現在の音楽録音のほとんどはこのデジタル的な録音。