
放送・電波
音は波の繰り返しで進む。山と谷の繰り返し。
下図の周期が1秒間に何回あるか、を周波数といい、1回ある時は1Hz(ヘルツ)という。

人が耳で聞くことのできる音の波(音波)を可聴音といい、
低い音は20(Hz)から高い音は20000(Hz)まで聞くことができる。
これは1秒間に20回の周期から、20000回の周期の音。
20000(Hz)以上を超音波という。
可聴音が低周波と呼ばれるのに対して、
無線に利用される電磁波(電波)の周波数は高周波と呼ばれる。
電波の種類
高周波は帯域によって、長波、中波、短波、超短波、極超短波などに分類される。
一般的なものは、
| 種類 | 周波数 | 用途 | 例 |
| 中波 | 0.3MHz〜3MHz | AMラジオ | 文化放送は1134KHz(1.134MHz) |
| 超短波 | 30MHz〜0.3GHz | FMラジオ | NHKFMは東京の場合は82.5MHZ |
| VHFテレビ(1〜12ch) | NHK総合は東京の場合、映像は191.25MHZ、音声は95.75MHZ | ||
| 極超短波 | 0.3GHz〜3GHz | UHFテレビ | UHFテレビは千葉テレビの場合、映像は663.25MHZ、音声は667.75MHZ |
| 地上波デジタルテレビ | NHK総合は東京の場合27(1ch)映像は555.25(MHZ)、音声は559.75(MHZ) | ||
| 携帯電話 | 主に800MHZ | ||
| 無線LAN | 主に2.4GHZ |
電磁波(電波)の伝わり方
磁力線が走ると起電力が生じる。起電力が生じると磁力線が走る。
この繰り返しで電波は進む。
磁力線は1本ではなく360度の球面上を走り、起電力も同様に球面上に生じる。
下図は、磁力線1本と起電力の方向1つをモデルにしている。
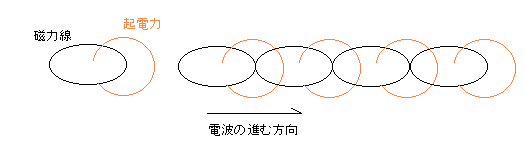
周波数による特性
周波数が低い(波長が長い)ほど、電波は遠くへ届く。
例えば、AMラジオの電波は、放送局から発射され、直接受信者側に届くものもあれば、
地上80km〜200Kmにある電離層で反射して地表に向い、
地表で反射して電離層へ、と反射を繰り返して到達するものもある。
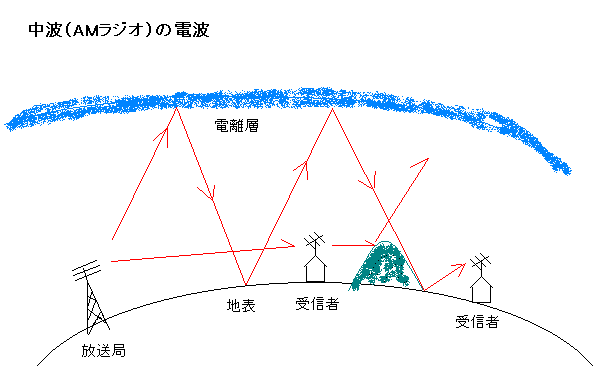
障害物があっても、反射波が届くのでより遠くへ進むことができる。
夜になると電離層の厚みが変化するので、より反射しやすくなり、
外国の電波が受信できることもある。
これに対して、周波数が高い(波長が短い)電波は、直線性が高いので、
電離層を突き抜けてしまう。直線で到達する電波は受信者側に届くが、
障害物があると、その先には届かない。
そこで、中継所を作り、その先へ電波を送っている。
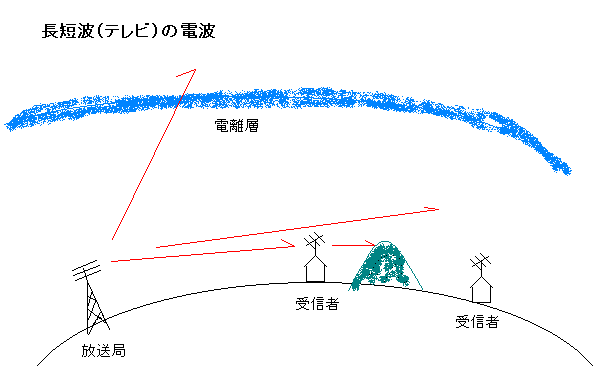
地上波デジタル放送
テレビ放送は、H20年現在はアナログ放送。信号がアナログ信号。
H23年にはアナログ放送は中止となり、テレビ放送の全てが地上波デジタル放送になる。
放送信号の種類が変わり、また使用する電波の周波数もより高い周波数に変わるので、
アナログ放送の受信設備(アンテナ、アンテナ線、テレビ受信機)では
デジタル放送は受信できない。
放送信号がデジタルになると、余計なものを切り捨てられるので、
使える周波数帯に空きがでる。そこに、番組情報や、緊急情報など、
テレビ放送以外の情報を送ることができる。
電話回線などを使えば、視聴者の側からデータを放送局に送信できるので、
双方向のやりとりができる。というのが地上波デジタルのメリットだと言われている。
しかし、
アナログ信号を扱う今までのテレビを、全てデジタル対応のテレビに買い換えるのは大変。
そこで、デジタル信号をアナログ信号に変換するアダプターを使用する。
家の中に入ってくるアンテナ線の大元にこのアダプターをつければ、
家の中のアナログ信号テレビでデジタル放送が見られる。
ただし、デジタル放送のメリットである双方向のやりとりはできない。
携帯電話の通話範囲
800MHz 帯、 1.5GHz 帯、 2.0 GHz 帯という直進性の強い周波数帯が使われているため、
高度の高い山の上では送受信できることがある。
しかし高速道路や集落から離れている山域や谷筋では全く使えない。