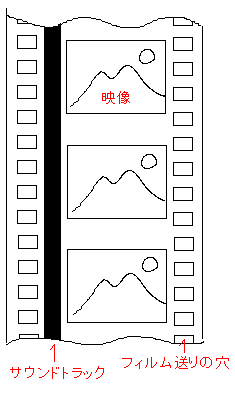
映像の記録
写真
目に見える映像を記録した最初の機械は写真。
最初はガラスの表面に映像を記録した。
その後プラスチックのフィルムに映像を記録するようになった。
現像、引き伸ばし、焼き付け、これらの作業をDPEと言う。
まず、
撮影したフィルムを暗室の中でケースから取り出す。
専用の薬剤を入れたトレイにフィルムを入れて画像を定着させる(現像)。
フィルムを乾燥させた後、機械に装着して光を当て(引き伸ばし)、
印画紙に引き伸ばして焼き付ける(焼き付け)。
こうした作業は素人には難しく、機材も高価だったので、写真屋さんにフィルムを出して、
出来上がりまで数日待つ、というのが一般的だった。
写真は当初はモノクロ(白黒)。その後カラー写真が一般的になった。
写真機は高価なものだったので、一部のマニアが使用していた。
その後、小型・軽量化され、自動焦点のカメラが開発された。
写真機とフィルムで昼間の撮影はできるけれど、夜は撮影できない。
そこでプラッシュライトを使用して、一瞬明るくして撮影した。
フラッシュライトは1回だけの使い捨て。
その後ストロボライトが登場。何回でもライトを点灯できるようになった。
時代は変わり、現像から焼き付けまでを全自動で行なう機械が開発され、
町のあちこちで「スピード写真」の看板を目にするようになる。
フィルムカメラとデジタルカメラ
フィルム写真はデジタルカメラ(デジカメ)の登場で利用者が激減。
フィルム写真は映像をそのままフィルムに記録する。
デジタルカメラは、映像をデジタルデータとして記録媒体(カード等)に記録する。
データなので、
再生・加工が簡単にできる。移動ができる。消去ができるなどの特性がある。
言い換えると、
デジカメは撮影した画像をその場で確認できる、何回でも取り直しができる、
パソコン(PC)で画像を見たり加工したり、印刷することができる、などの利点があり、
現在ではデジカメが主流になっている。
ただし、画像の鮮明さではフィルム。一般的なサービスサイズの写真では変わりはないが、
大きなポスターなど、画像を拡大した場合、フィルム写真の方がきれいにできる。
映画
フィルム写真の映像のひとコマひとコマを続けて映写することで、
動く映像として見るようにしたものが映画。
映画は35mmや16mmの幅のフィルムで作られていて、最初は映像だけ。
無声映画と呼ばれた。
後に音声の記録をフィルムの端につけて再生できるようになった。。
音声の記録は磁気で行い、フィルムに後から磁気テープを貼り付ける、
撮影と同時に貼り付けるなど、録音・再生方法は色々あったらしい。
フィルムのほとんどの部分は映像で、端っこに縦に音声の通り道がある。
この音声の部分をサウンドトラックと言い、映画音楽のサントラ版というのは
これのこと。
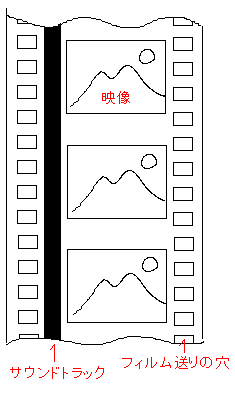
家庭用の動く映像記録は、8ミリ映写機。当初は映画同様に映像のみ再生。
フィルムの幅が8mmで、カメラにフィルムを装填。撮影して写真屋に現像を依頼。
映写機にセットして映像・音声を楽しんだ。
これも高価なものだったので一般的には浸透せず、
マニアが家族の記録映像などとして使っていた。
ビデオカメラは当初は大形だった。三脚に固定したり、肩に担いで使用。
ビデオデッキが市販されてから広まった。
ビデオテープデッキ
開発当初のビデオテープデッキ(ビデオデッキ)は、
音の録音再生機械のテープデッキと同様に、初めはオープンリール型だった。
大型で高価であり、教育用などに使われ、市販されてもあまり広まらなかった。
昭和50年(1980年)代にソニーがベータ方式を開発。
従来より小型で市販されたが、まだ高価であり、一部のマニアにとどまっていた。
用途は主に行事などの映像をカメラで撮影して保存していた。
ソニーがベータ方式で市場を独占した後、
松下、ビクター、東芝、シャープなど他のメーカーは
ベータ方式以外の方式でビデオデッキの開発を進め、
その内、ビクターがVHS方式を完成。
ビクターはこの方式をソニー以外の各社に公開。
時計のタイマーが得意なもの、テレビチューナーが得意なもの、
リモコン機能が得意なものなど、各社が得意な分野で特性を出して開発を続け、
ソニー以外のメーカーがVHS方式の新製品を売り出した。
ソニーのベータ方式より安価で多機能装備のVHS方式は市場に広まり、
数年後にはベータ方式と立場が逆転。
ビデオ方式はVHSが世界規格になり、ソニーはベータ方式を放棄。
VHSが市場に広まったことでテレビ録画が一般的となり、
ビデオテープで映画が販売され、後にレンタルされるようになる。
ビデオテープの映像・音声の質をより向上させたのが、再生専用のレーザーディスク。
映画の他、カラオケなどにも利用されたが数年で姿を消す。
その後にDVDが登場。
ビデオカメラ
個人的な映像の記録では、カメラもビデオデッキも当初はアナログ映像。
映像を磁気テープに記録して再生していた。
ソニーのビデオカメラ、ハンディーカムが発売されて一般に広まった。
これはパスポートと同じサイズの小型で、携帯用ビデオカメラとして旅行に持参できた。
映像をVHSのビデオテープにダビングして保存するのが一般的。
その後デジタルビデオカメラが登場。
デジタルデータをテープに保存し、アナログであるVHSビデオテープに保存。
映画などのDVDが広まり、デジタルビデオカメラもDVDに録画するもが登場。
映像を保存する媒体はDVDからデータカードに変わり、小型化が図られた。
携帯電話
携帯電話が普及し、カメラが搭載されるのが一般的になると、
携帯カメラで写真やビデオも撮影できるようになり、
その動画を携帯メールで送信することができるようになる。
携帯電話の着信音も、当初は着メロだったが着うたに進化し、
音楽を携帯電話でダウンロードして聴くことが広まる。
その後音楽と映像を携帯電話で楽しむようになり、
映像を観るための機械はビデオデッキ、パソコンの他に、
携帯電話が含まれるようになった。