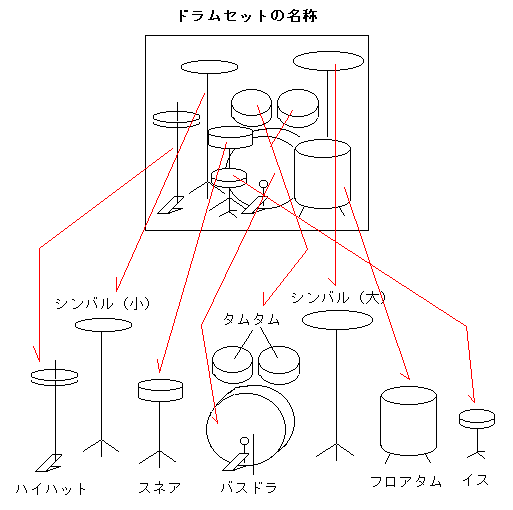
ドラム入門 (17.1.19〜18.1.11更新)
はじめに
もう20年も昔、当時知り合いだった中学生にドラムを教えてもらいました。
基本がわかれば後は感性(センス)です。
ここでは、私なりの解説をまとめました。
正式に覚えたわけではないので、本来のたたき方とは違うと思います。
それなりにできればそれでOKという、極めて安直な内容ですが、
何かの参考になれば幸いです。
ドラム各部の名称
一般的なドラムのセットと各部の名称は下図のようになっています。
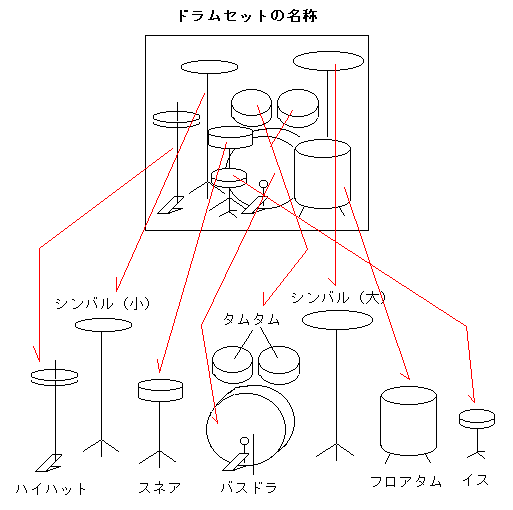
このセット内容の全てがないと駄目だ、という訳ではありません。
曲によっては、スネアとハイハットで間に合うものもあります。
ドラムのどういう音が必要とされているかで、セット内容が変わります。
動きと叩き方
叩く手が右手か左手かは、曲によって違ってきます。ここではあくまで基本を解説。
ハイハット
ペダルを左足で踏んだ状態で叩くと、チッチッチという固い音。
これは主にリズムを通しで刻みます。左側にありますが、右手で叩きます。
ペダルを離す(足を上げる)と、チャンチャンチャンと響く音になります。
シンバル(小)
シャ〜ンという音。右手で叩きます。
シンバル(大)
チンチンという硬い音。ハイハットの代わりにリズムを通して刻みます。
スネア
鼓笛隊の太鼓の音。
正面にあります。通しのリズムの中で叩く時は左手で叩きます。
トコトコとローリングする時は両手で叩きます。
タムタム
左が高い音。右が低い音。トコトコと両手で叩きます。
バスドラ
右足で踏んで叩きます。音はドンドン。
シンバル(大)
チッチッチッチと叩きます。
ハイハットの代わりにリズムを通しで刻みます。
右手で叩きます。
フロアタム
タムタムよりは低い音。ドコドコ。両手で叩きます。
練習の準備
用意するもの
スティック或いは棒(菜箸でも何でも可)2本、週刊漫画雑誌(厚手の物)、
漫画を置く台になるもの2個(ゴミ箱など)、椅子
スティック:楽器店で500円〜1000円で売っています。
木製、プラスチック製、など色々あります。太さや形も様々です。
初心者の練習に使うので、軽くて細く、握りやすいものを選びます。
わからなければ、店員にききます。
「初めてで、練習に使いたい」と言えばわかります。
配置
イスに座って、正面に漫画本(スネア)、左に漫画本(ハイハット)
スネアの高さは、肘から手の先までが水平よりちょっと下がった位置。
ハイハットの高さは、左肘よりちょっと上の位置。

練習1
4拍子
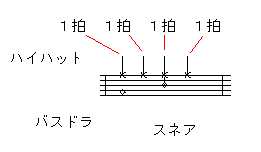
ハイハット(右手)は 1 2 3 4 と1拍ずつ(左にある漫画本を)叩きます。
ハイハットのペダル(左足)は踏んだ状態。
スネア(左手)は、3拍目に(右にある漫画本を)叩きます。
右手を上に両手を交差させて、
右手でゆっくり 1 2 3 4 1 2 3 4 ・・・ と
漫画本(左のハイハット)を繰り返し叩いて、
右手が3の時に、同時に左手で漫画本(スネア)を叩く。
これはできると思います。何回かやって慣れたら、これに右足を加えます。
バスドラ(右足)は1拍目に踏みます。ハイハットの1拍目と同時。
踏んだ後は、次に踏むまでつま先を上げたままにします。
実際の音
4拍子
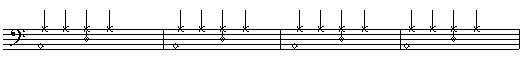
4拍子の音
※注1
上図では、楽譜を書くソフトの都合で、
バスドラの音符の位置が少し左にずれています。
バンドスコアなど、実際には1拍目のハイハットと同じ位置で表示されています。
練習曲 1) チューリップ
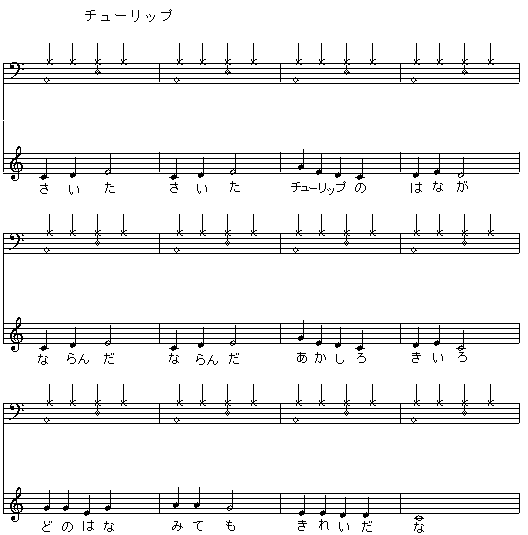
チューリップの音
練習2
8拍子(8ビート=エイトビート)
4拍子の2倍の速さ(※注2)。1小節に8つの音の区切りがあって、
ハイハットは 1 2 3 4 5 6 7 8
スネアは 3 7
バスドラは 1 5
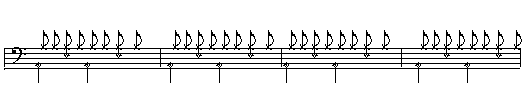
8ビートの音
練習曲 2) 8ビートのチューリップ
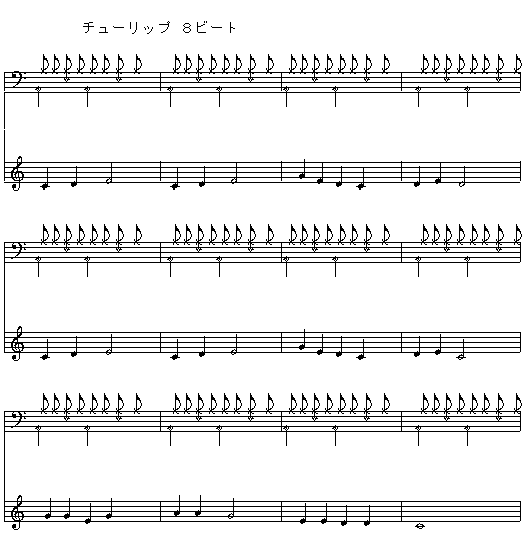
※注2
音の速さ
練習曲の4拍子と8拍子は、厳密には倍の速さにはなっていません。
基本となるのは、メトロノーム。
1拍=4分音符1つ の音の長さを数値で表わします。
一般に、楽譜の左上に、数字で100とか120とか書いてあります。
練習曲の場合は、4拍子は1拍=120 8拍子は1拍=100 の速さの音です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ドラム練習 その2 (18.1.11)
今回は、飾りやアクセントを取り上げて解説します。
ドラムの叩き方の全体像は、基本のリズムに飾りやアクセントを加えたものです。
飾りやアクセントには、
スネアーやタムタム、バスドラ、シンバル等が関わっています。
叩くタイミングを変えたり、ローリング=トコトコと続けて叩いたりします。
スネアー:
8拍子(8ビート=エイトビート)
4拍子の2倍の速さ。1小節に8つの音の区切りがあって、
ハイハットは 1 2 3 4 5 6 7 8
スネアは 3 4 7
バスドラは 1 5
口で言うと「ズン、チャチャ、ズン、チャ」
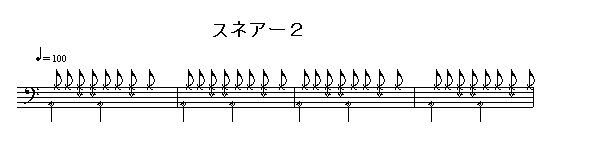
この叩き方を使っている曲=荒井由美「ルージュの伝言」
例えが古くて申し訳ありません。聞いてもらえば分かります。
ローリング:
トコトコ・・・とスネアーとタムタムを2回ずつ、或いは4回ずつ、
スネアーからタムの高い方、低い方へと叩くことを言います。
ローリングの次のハイハットの1の部分を左シンバル(響く音)で叩く。
下図はローリングの一例。ローリングはスネアだけでも構いません。

※左シンバルのこの表示は正確ではありません。
ここでは1拍目に叩く、という意味で理解してください。
バスドラ:
基本は1と5ですが、ずらして、1と4と6で叩く。
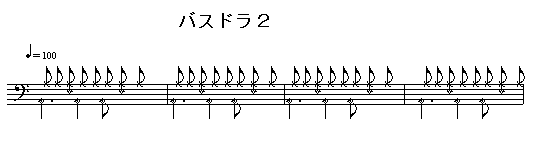
等‥これらの組み合わせで結構曲らしくなります。
上記の解説の内、バスドラ以外を適当に加えて構成したのが
次のチューリップ2。
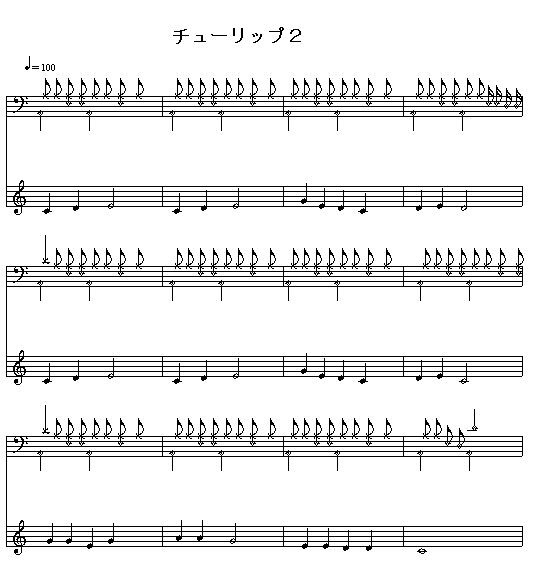
速さを上げて、ローリングを細かく、最後の段の3小節はバスドラを変えてみた例。
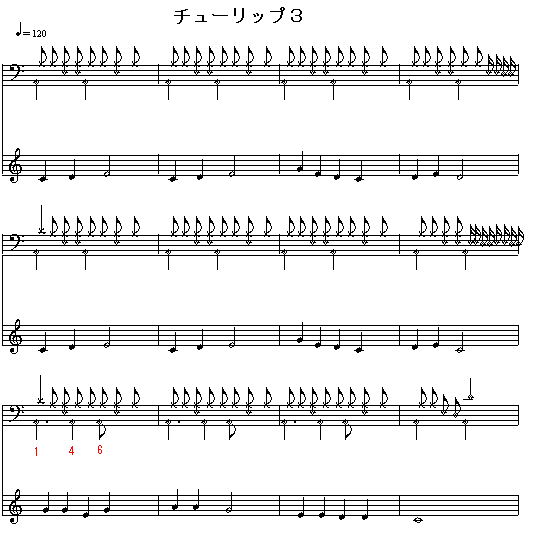
その他、
シンバル(大) 1 2 3 4 5 6 7 8
スネア 3 7
ハイハット 3 7
8拍子でハイハットを8つ叩く部分を、シンバルの大で叩く。
シンバルで2を叩いたらハイハットを上げ、
スネアを3で叩く時、同時にハイハットを踏む。
など、飾りやアクセントはこの他にも色々あります。
この先
あとは曲ごとにどう叩くか、という段階になります。
「この曲のドラムを叩きたい」という曲がある場合、
とにかく繰り返し何度でも耳で聞いて、どう叩いているのか、を探してみる。
基本は同じなので、ある程度が分かったら、
その雰囲気に近い叩き方を自分で探してみる。
正確なコピーをしたいのなら楽器店にいって、曲ごとのタブ譜を見ればわかります。
ただし、最近はデジタル音楽が流行っていて、
実際には出せない音をコンピューターで作って使っている場合があります。
太鼓とシンバルのドラム=アナログ音楽にこだわるなら、
それなりの叩き方を自分で探すしかないのかも知れません。
練習曲
ドラムの練習に適していると私がお勧めするのは、ベンチャーズです。
これも古くて申し訳ありません。
シンプルだけれど、色々な音の組み合わせで出来上がっています。
ドラムだけではなく、エレキギターの教則本としても、ベンチャーズは最適です。
機会があったら一度聞いてみてください。
「パイプライン」「ダイアモンドヘッド」など、一度は聞いたことがあるかもしれません。
ダイアモンドヘッドは以前、アニメこちかめのエンディングで使われていました。
ドラムの特殊性
ドラムを練習する場合、雑誌などの代用品で動きを身につけて、
実際にドラムを叩いて練習するのはレンタルスタジオや、
民家から離れた個人の練習場、ということになります。
自宅でドラムの音を出して練習するには、防音の部屋でないとできません。
練習自体にはあまりお金はかかりませんが、
持ち運びは大変だし、実際に叩くには場所が限定される楽器です。
しかし、基本がわかれば応用は楽だ、と思います。
ドラムは曲全体のリズムキープです。叩く人のセンスが問われます。
問題はリズム感。
終わりに
「ドラムをやってみたい」という知り合いに、
基本を教えるためにまとめたのが始まりでした。
更新は未定、として気が付いたら1年が過ぎようとしています。
その知り合いがそれ以上を知ろうとしなかった、という結果ですが(笑)
今年18年の元旦に、このページを見た方から「更新はまだですか」
というご意見をいただき、中途半端に残していたものを追加更新しました。
18.1.11