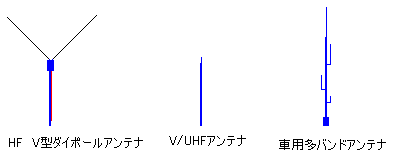
災害時のためのアマチュア無線 入門 その2
(23.5.5)(最終更新:23.11.22→30.1.15)
交信の準備 ※ここからは開局免許状が届いてからの話です
開局免許状が届いてコールサイン(呼び出し符号)が決まったら交信ができます。
無線機とアンテナ、アンテナケーブルを接続して無線機の電源をいれ、目的の周波数に合わせます。
非接地型アンテナ(ノンラジアルアンテナ)を使用する場合は、アース接地は不要です。
接地型アンテナ(ラジアルアンテナ)を使用する場合はアース接地が必要です。詳細は後述。
また、SWR調整をして目的の周波数を合わせて交信できます。詳細は後述。
アンテナ調整を自動で行ってくれるオートアンテナチューナーというものも売られています。
交信の実際
詳細は試験の参考書に記載してあります。ここでは極簡単に手順を説明します。
交信には、不特定の相手を呼び出す場合と、特定の相手を呼び出す場合があります。
1.不特定の相手を呼び出す 7Mhz(呼び出し周波数なし)の場合
自分がCQ発信する場合と、他者のCQ発信に応答する場合があります。
自分がCQ発信
自分のコールサインがJA1ABCの場合、
自分:「CQ、CQ、こちらはJA1ABC、ジャパン、アルファー、ワン、アルファー、ブラボー、チャーリー、
どなたかお聞きの局長さんがいらっしゃいましたらコールをお願いします。
CQ、CQ、こちらはJA1ABC、ジャパン、アルファー、ワン、アルファー、ブラボー、チャーリー、受信します」
と呼びかけます。
※コールサインのJA1ABCなどのアルファベットは、電波状態の変化で聞き間違いが起きます。
特にAとE、CとT、KとQなど間違えやすいのでそれを防ぐために
「欧文通話表」を使ってJはジャパン、Aはアルファーなど、決まったカタカナの言葉で相手に伝えるのが決まりです。
欧文通話表は後に掲載してありますが、インターネット上を検索すれば掲載されています。
これは実際に交信する時に参考にすれば自然に覚えます。
CQ発信に応答する(自分が応答する側の場合は、相手側だと思ってください)
自分がJA1ABC、相手がJA1DEFの場合、
自分(こちら)のCQを聞いて、相手が応えます。
相手:「こちらはJA1DEF、ジャパン、アルファー、ワン、デルタ、エコー、フォックストロットです、どうぞ」
自分:「JA1DEF、こちらはJA1ABCです。応答ありがとうございます。
シグナルレポートはファイイブナイン5、9をお送りします。JA1DEF、こちらはJA1ABCです。どうぞ」
相手「レポート5、9、ありがとうございます。こちらも5.9をお送りします。JA1ABC、こちらはJA1DEFです。どうぞ」
自分「5,9ありがとうございます。こちらのQTH(住所)は千葉県市原市です。オペレーターは○○と申します。」
CQに対して、応答側はまず自分のコールサインを伝えます。
それをCQ側が受け取れば、CQ側は、応答側(相手)のコールサインを言ってから自分のコールサインを言います。
これは「○○さんへ、こちらは○○です」と相手を特定して発言しますよ、いう意味です。
CQに応答する人が一人とは限りません。同時に複数の人が応答する場合は珍しくないので、
応答してくれた人の中で一人を特定して返事をします。
その後の交信内容は色々です。
お互いの住んでいる地域や名前、無線設備の紹介など相手との話の進み方で内容は変わります。
ただし、CQに応答する人が複数いる場合は、一対一での交信が長くなると他の人を待たせることになるので、
シグナルレポートの他簡単な交信で終わらせることが多くなります。
他に待っている人がいなければ交信の時間的な長さは自由です。
※ シグナルレポートとは、相手の声の聞きやすさ、了解度(1〜5)と相手の電波の強さ(1〜9)のこと。
了解度は主観、感じたままでOK。電波の強さは無線機の表示で判断します。
了解度と強さは日本語数字読み、或いは英語読みで伝えます。 5、9(ゴー・キュー)或いはファイブナインは最高の状態をいいます。
交信成立の最低条件はシグナルレポートの交換です。言葉で伝え合えばOKです。詳細は後に掲載してあります。
※長時間交信を続ける時には10分に1回、自分と相手のコールサインを伝える、という決まりがあります。
これは無資格者が違法に電波を利用することを避け、資格者も自分の電波の出所を明らかにする、などの意味があります。
2.特定の相手を呼び出す
相手のコールサインがJA1DEFの場合、
「JA1DEFいらっしゃいますか?こちらはJA1ABCです」
相手が応答した後は普通の会話(通信)でやりとりします。
不特定の相手を呼び出すー2
呼び出し周波数がある場合 144Mhzの例
あらかじめ通話できる周波数を探しておきます。例えば145.60Mhzで誰も交信していない場合、
念のために「この周波数をお使いでしょうか」と数回呼びかけて返事がないことを確認します。
それから呼び出し周波数の145MhzでCQ発信します。
「CQ、CQ、こちらはJA1ABC、ジャパン、アルファー、ワン、アルファー、ブラボー、チャーリー、
どなたかお聞きの局長さんがいらっしゃいましたら、次回145.60、145.60で再度コールします。移動します」
すぐに145.60Mhzに合わせて再度
「CQ、CQ、こちらはJA1ABC、ジャパン、アルファー、ワン、アルファー、ブラボー、チャーリー、
どなたかお聞きの局長さんがいらっしゃいましたら応答お願いします。受信します」
と呼びかけます。
交信時の注意
使用する電波帯によって、呼び出し周波数と非常通信周波数が決まっています。
呼び出し周波数
3.5、7、21MhzなどのHF帯では呼び出し周波数はありません。
50Mhz以上の周波数では呼び出し周波数が決まっています。
50Mhzでは51.00Mhz、144帯では145Mhz、430帯では433Mhzが呼び出し周波数です。
CQを呼びかけて交信相手を探す場合、特定の相手のコールサインを呼びかけて交信する場合など、
交信相手を呼び出すために使う周波数を呼び出し周波数といいます。
相手が決まったら、呼び出し周波数以外で空いている周波数に移動して交信を続けます。
呼び出し周波数は呼び出すだけで、実際の交信は別の場所で、というのが決まりです。
非常通信周波数
各周波数帯では非常通信に使用する周波数が決まっています。一部を抜粋すると、
| 周波数帯 | 非常通信周波数 | 周波数帯 | 非常通信周波数 | |
| 3.5Mhz | 3.525±0.005Mhz(5Khz) | 144Mhz | 145Mhz(呼び出し周波数と同じ) | |
| 7Mhz | 7.030±0.005Mhz(5Khz) | 430Mhz | 433Mhz(呼び出し周波数と同じ) | |
| 50Mhz | 51.00Mhz(呼び出し周波数と同じ)、51.50Mhz |
詳細は後に掲載してあります。
アマチュア無線の交信の色々
不特定多数の相手と交信し、シグナルレポートを交換。
そのままで交信終了でも構いませんが、どこの相手と交信したのかの記録として、
QSLカード(交信証)をやりとりすることがあります。
QSLカード
QSLカードには、交信の日時、周波数、シグナルレポート、使用無線機、アンテナ、自分の居住地などを記載します。
このカードを集めることを目的に交信している人が沢山います。
交信しているお互いが直接郵送し合うのは料金も高額になります。
そこでJARL(日本アマチュア無線連盟)が配送を代行しています。
交信相手同士がJARLの会員であれば、まとめてJARLに郵送すれば各会員にまとめて郵送してくれます。
JARLの入会費、年会費はJARLのページを参照。http://www.jarl.or.jp/index.html
コンテスト
主催は団体や個人で、「一定期間内にどれだけの数の交信ができたのか」を競うものや、
「どれだけ沢山の地域と交信できたか」を競うものもあります。ルールは主催者によって色々です。
コンテストの交信はお互いのコールサインとシグナルレポートの交換などで交信を終了します。
アワード
アマチュア無線では日本国内を10の地域に分けています。
国内の各地域や県、市、郡など一定の数の地域と交信が成立した場合に申請すれば表彰されます。これがアワード。
これは海外の各国や地域でも同様の表彰があります。主催は各団体。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
固定・モバイル用無線機
アンテナのアース(周波数的アース)
アンテナというとテレビやラジオのアンテナを思い浮かべます。
これらは受信だけのアンテナです。受信だけならアースは必要ありません。
無線では電波を受信したり、電波を発信します。電波を発信するためにはアンテナの状態を調整する必要があります。
アースというと一般的には感電防止のアースを言いますが、
無線機の場合は周波数的なアースのことを言い、アンテナが電波を発信するために必要なアースのことです。
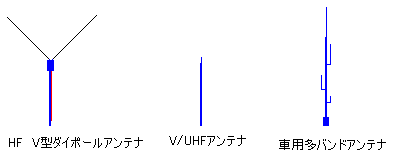
※非接地型アンテナ(ノンラジアルアンテナ)の場合はアースの必要はありません。
V字アンテナ(アース不要)
HF用V型短縮ダイポールはV字になっています。
7、21、28Mhzが一緒になったV字が3つある多バンドアンテナもあります。
HF〜50Mhz用アンテナでV字にできるアンテナは非接地型アンテナ(ノンラジアルアンテナ)と言い、アースはいりません。
下図は3.5/7MHz帯V型ダイポールアンテナ(DIAMOND)

下図は7/14/21/28/50MHz帯短縮V型ダイポールアンテナ(DIAMOND)

これらのアンテナはアース不要です。
HF帯やV/UHFの短縮アンテナで、Vではなく1本のものもあります。
形が1本で説明書に「接地型アンテナ」と書いてある場合は、アースを取る必要があります。
1本でも非接地型アンテナがあります。この場合はアース不要です。
車用モービルアンテナ
車用モービルアンテナは車のボディをアースにします。
このアンテナを建物のベランダに設置する場合は、やはりアース接地が必要です。
アース接地
鉄筋の建物でベランダが鉄筋などに接続されている場合はベランダがアースの取り付け場所になります。
アースが取れない場合は、代わりになるものを用意します。
※代用のアース接地に関してはインターネット上を検索したり、書籍も出ていますから参考にしてください。
代用アース接地の例
1、導線
300÷周波数÷4×0.95=アース線の長さ
| 3.5Mhzの場合、300÷3.5÷4×0.95=20.3m 7Mhzの場合、300÷7÷4×0.95=10.1m 50Mhzでは1.4m |
3.5Mhzの場合、家庭用電源コード(平行コード)10mをホームセンターなどで購入。
2本のコードを1本ずつに引き裂いて片方の端同士を接続して、20mの1本のコードにします。
これをアンテナの取り付け基台にボルト・ナットで固定し、コード全体をベランダに置きます。
これでアースは完了です。
2、バーべキュー用の金網
面積が1平方メートル以上の金属面をアースの代わりに使います。
バーベキュー用の大きな金網を4〜6枚購入。これもホームセンターで売っています。
金網を並べて重なる部分を2箇所ずつ銅の裸線で縛って固定しますが、
縛る部分をあらかじめ紙やすりでこすって、金網の塗装をはがしておきます。
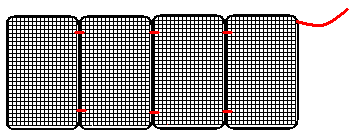
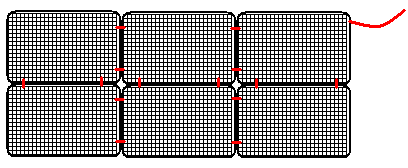
銅線で縛って固定したら金網と銅線を半田付けします。ビニール被覆コード1本も半田付けし、
アンテナの取り付け基台にボルト・ナットで固定。これでアースは完了です。
金網をアンテナの近くでベランダの邪魔にならない場所に置いて固定します。
アース不要のアンテナ
HFで、V字型アンテナなど非接地型アンテナ(ノンラジアルアンテナ)の場合はアース接地の必要性はありません。
V/UHF(144、430Mhz)で非接地型アンテナ(ノンラジアルアンテナ)の場合はアース接地の必要性はありません。
HFでもV/UHFでも、非接地型アンテナ(ノンラジアルアンテナ)以外の接地型アンテナを使用する場合は、
アース接地が必要です。
固定・モバイル用無線機
アンテナ調整の実際 ※これは開局免許状が届いてからの作業です。
アンテナから電波を送信するのに適した状態にするために、アンテナ調整(SWR調整)が必要です。
しかしこれは初心者には難しいので、
無線に詳しい人やハムショップの店員に実際の操作を教えてもらってから行う方が無難です。
地域の無線クラブには無線の愛好家がいますから相談することもできます。
インターネット上の検索サイトで地域の無線クラブを検索してみてください。
HF帯のSWR調整
SWR計は、無線機からの電波の進行波とアンテナからの反射波の割合を表示します。
進行波が大きく、反射波が小さい場合は損失が少ない状態であり、SWRの値は1.5以下となります。
損失が少ない状態で電波が発射されるのが理想です。
SWR値が1.5以上の値だと、損失が大きい状態なので、
発射される電波の電力が小さくなり、電波は遠くまで届きません。
送信信号がアンテナから放射されるために丁度良く調整された状態にするのがSWRの調整です。
SWR計
アンテナ調整にはSWR計を使用します。(約8000円〜)
下図のメータの場合、左からの針と右からの針の交差する所を見ます。
メモリの中の右側、緑の範囲ならSWRが1.5以下ということになります。

アンテナの説明書を参考に、SWR値が1.5以下になるように調整します。
HF短縮ダイポールアンテナの場合
アンテナの説明書を参考に、アンテナの長さや調整部分を標準の位置に調整します。
SWR計はアンテナの近くで測定するので、
短いケーブル(例として)2〜3m1本、1m1本を用意。それぞれ両端にコネクターを半田付け。
SWR計の説明書を参考に、
アンテナ→2〜3mケーブル→SWR計→1mケーブル→無線機
という形で接続します。
SWRはアンテナの直下で測定するのが基本なので、
アンテナがベランダにある場合は無線機をベランダに移動して作業をすることになります。
当然電源の延長コードも必要です。
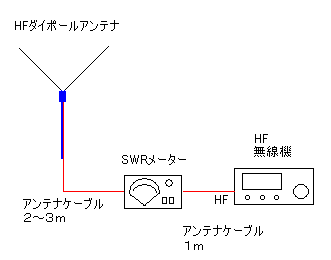
例)7MHz 短縮ダイポールアンテナの場合
交信で使用できる周波数帯は7.035〜7.200までと決まっています。
無線機の周波数表示を7.100、無線機の出力を5W以下にして、電波形式はFMを選択。
プレストークボタンを一瞬押して(発信して)、SWR計の値を見ます。
7.100で一瞬発信。数値を見て、次に7.150で発信、とポイントで発信して数値を見ます。
こうやって7.100を中心に、SWRが1.5以下になる範囲をメモします。
もし、高い周波数で1.5に近くなる場合は、アンテナの長さが短い状態。
低い周波数で1.5に近づく場合は長さが長い状態です。
7.100でSWRが1.5になるように、高い周波数の場合はアンテナを長く、
低い周波数の場合はアンテナの長さを短く調整します。
アンテナの説明書を見ながらアンテナの長さや調整部分の位置の調整をして、1.5以下になる所を見つけます。
標準の位置から1cmずつ長く(短く)してSWR値を見ます。
7.100でSWR=1.5以下になるように調整できたら、1.5以下になる範囲を見ます。
例えば7.090〜7.120MHzの間でSWRが1.5以下に調整できたとします。
この場合、この周波数の範囲内であれば損失が少なく発信ができる、
ということになります。
この範囲が広ければそれだけ発信できる範囲が広くなります。
電波の発信できる範囲
実際の交信では、SWR=1.5以下になる範囲の周波数で発信します。
この周波数の範囲が狭いと、発信できる範囲が狭い、ということになります。
例えば7.090〜7.120でSWR=1.5以下、
7.080から下ではSWR=∞(無限大)、7.130から上でも無限大の場合、
7.090〜7.120の間であれば交信できる状態です。
7.090でCQを呼びかけられたら応答できます。
相手の電波が強くてこちらには届いても、こちらの電波が相手に届くかどうかはわかりません。
場合によってはこちらの呼びかけが届かないこともあります。
7.060でCQを呼びかけられて応答しても相手には届きません。
7.060で交信するには、7.060でSWR=1.5以下になるように
アンテナの長さや調整部分を調整しなおす必要があります。
SWR=1.5以下になる周波数の範囲が広ければ、交信できる範囲が広くなりますが、
逆の場合は交信できる範囲が狭くなります。
これでは不便なので、この状態を解消するために、アンテナチューナーを使用します。
※アンテナチューナーは必需品ではなく、交信できる範囲だけで交信するなら必要はありません。
調整が済んだら実際に発信
SWR計を外して通常の配線状態にします。
アンテナをしっかり固定し、無線機を室内に移動してアンテナケーブルを接続。
電波出力を4級の範囲HF10W、30Mhz以上20Wに設定して通常の交信をしてみます。
最初はCQ発信している人に応答してみるのがベストです。
アンテナチューナー
2〜3万円。発信周波数とアンテナの状態を自動的に調整してくれます。
ただし、アンテナ調整でSWR=1.5以下になっていないと効果がありません。
また、使用するアンテナや環境によって効果は様々なようです。
アンテナチューナーには、屋外型と屋内型があります。
SWRの調整は、本来はアンテナ直下でするものなので、屋外型が理想です。
しかし、屋内型もそれなりに効果はあるようです。
屋外型はアンテナの直下、或いは近い位置に設置します。
コンセントが屋外にない場合は、電源コードを室内から屋外へ出して接続することになり、防水処置が必要になります。
屋内型は無線機のそばに設置します。
以前の割り当て周波数では、
7Mhzで使用できる周波数範囲は7.035〜7.100でした。
それが数年前に7.035〜7.200に拡張されました。
私の場合、
無線機はバーテックスのFT857DM。これは7Mhz拡張の調整済みですが、
アンテナは7Mhzバンドが拡張される前に買ったものを使用しています。
つまり7.100Mhzまでを扱うアンテナです。
この無線機には専用のアンテナチューナー(屋内型)が別売りされていて、
試しに使ってみた所、従来のアンテナで7.200Mhzまで交信ができました。
本来は、拡張以前のアンテナには拡張に対応する部品を後付けする必要があります。
実際のアンテナ調整や無線機に関する説明はここまでです。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ここまでで一区切り。
非常災害時の通信手段として無線を利用するために、最低限必要なものを揃えて
とにかくアマチュア無線を始めるにはどうしたら良いか、についてまとめてみました。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ここからは、
第4級アマチュア無線技士免許を取得して開局免許状が届いた後、
実際にアマチュア無線を利用する上で知っているべきこと、知っていると便利なことなどを説明します。
4級で利用できる周波数帯は、HF帯3.5〜8Mhzと21〜30Mhz(10W)。30Mhz以上(20W)。
バンドプラン(割り当て周波数)
http://www.jarl.or.jp/Japanese/A_Shiryo/A-3_Band_Plan/A-3-1-20090330.htm
アマチュア無線で使用できる周波数帯それぞれに用途が決められています。
一部を抜粋
7Mhzは以下のようになっています。
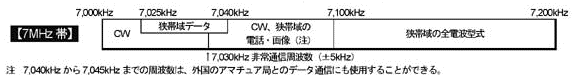
第4級アマチュア無線技士で関係しているのは「狭帯域の電話」です。
狭帯域とはSSBのことで無線機で7Mhzに合わせ、モードをLSBにした場合です。
通常はこのモードで交信します。電話とは言葉での会話のことです。
交信できる周波数の範囲は7.030〜7.200までの間。7.030は非常通信周波数なのでそれ以上上を利用できます。
CWはモールス通信(電信)のことで4級では利用できません。3級以上で利用できます。
144Mhzと430Mhzは下図。
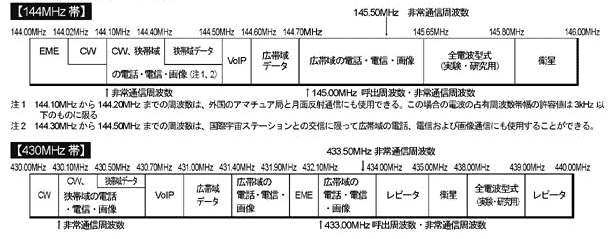
144では、モードがUSBなら144.10〜144.50Mhz。モードがFMなら144.60〜145.65Mhzまでの間。
呼び出し周波数は145.0Mhz。非常通信周波数は145.0と145.5Mhz。
430では、モードがUSBなら430.10〜430.70、モードがFMなら431.40〜431.50Mhzと432.10〜434.00Mhzの間。
呼び出し周波数は433.00Mhz。非常通信周波数は430.10と433.00と433.50Mhz。
シグナルレポート
R−了解度(Readability) |
|
S−信号強度(Signal Strength) |
|
欧文通話表
| A | ALFA | アルファ | N | NOVEMBER | ノベンバー | |
| B | BRAVO | ブラボー | O | OSCAR | オスカー | |
| C | CHARLIE | チャーリー | P | PAPA | パパ | |
| D | DELTA | デルタ | Q | QUEBEC | ケベック | |
| E | ECHO | エコー | R | ROMEO | ロメオ | |
| F | FOXTROT | フォックストロット | S | SIERRA | シエラ | |
| G | GOLF | ゴルフ | T | TANGO | タンゴ | |
| H | HOTEL | ホテル | U | UNIFORM | ユニフォーム | |
| I | INDIA | インディア | V | VICTOR | ビクトリー | |
| J | JULIETT | ジュリエット | W | WHISKEY | ウィスキー | |
| K | KILO | キロ | X | X-RAY | エックスレイ | |
| L | LIMA | リマ | Y | YANKEE | ヤンキー | |
| M | MIKE | マイク | Z | ZULU | ズール |
和文通話表
無線通信では電波の状態で聞き間違いが生じたり聞きにくかったりします。
例)こちらのQTH(住所)は千葉県市原市です。いろはのイ、ちどりのチ、はがきのハ、らじおのラ。
市原市です。オペレーターは「しばづけ」と申します。
新聞のシ、はがきのハに濁点、つるかめのツに濁点、景色のケ、しばづけと申します。
| ア | 朝日のア | ツ | つるかめのツ | モ | もみじのモ |
| イ | いろはのイ | テ | 手紙のテ | ヤ | 大和のヤ |
| ウ | 上野のウ | ト | 東京のト | ユ | 弓矢のユ |
| エ | 英語のエ | ナ | 名古屋のナ | ヨ | 吉野のヨ |
| オ | 大阪のオ | ニ | 日本のニ | ラ | ラジオのラ |
| カ | 為替のカ | ヌ | 沼津のヌ | リ | リンゴのリ |
| キ | 切手のキ | ネ | ねずみのネ | ル | るすいのル |
| ク | クラブのク | ノ | 野原のノ | レ | れんげのレ |
| ケ | 景色のケ | ハ | はがきのハ | ロ | ローマのロ |
| コ | 子供のコ | ヒ | 飛行機のヒ | ワ | わらびのワ |
| サ | 桜のサ | フ | 富士山のフ | ヰ | ゐどのヰ |
| シ | 新聞のシ | ヘ | 平和のヘ | ヱ | かぎのあるヱ |
| ス | すずめのス | ホ | 保険のホ | ヲ | 尾張のヲ |
| セ | 世界のセ | マ | マッチのマ | ン | おしまいのン |
| ソ | そろばんのソ | ミ | 三笠のミ | ゛ | 濁点 |
| タ | 煙草のタ | ム | 無線のム | ゜ | 半濁点 |
| チ | ちどりのチ | メ | 明治のメ |
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
実際にアマチュア無線を始めてからの色々
トラブルと対処
無線をしている人それぞれに特有の環境があります。
郊外に住んでいる人、市街地に住んでいる人、一戸建ての家に住んでいる人、集合住宅に住んでいる人、
一人ひとり環境が違います。
同じ無線機とアンテナを使用しても、その環境によって電波の送受信の程度には違いがあります。
それぞれの環境に合った無線設備を整える必要があります。
アンテナや無線機の設置でうまく行かなかったり、困った場合は先輩の意見が参考になります。
実際に無線を始めると、知らないことが沢山あって迷います。
何十年も続けているベテランもいれば全くの初心者もいて、そうした色々な人が同じ電波を利用しています。
迷ったり困ったりした場合は自分でできる範囲で調べる必要はありますが、
どうしても分からなかったら先輩に相談する方が話が早くて確実です。
地域の無線クラブや知り合いの無線家がいればそちらに相談することもできます。
インターネットでチャットをする人の場合は、yahooチャットでアマチュア無線の部屋があります。
私もお世話になっています。
電波障害
アマチュア無線で扱う電波は近隣の家に影響を与える場合があります。
電波障害にはテレビの映像に縞模様が入ったり、インターホンやパソコンなどの電化製品に影響を与えることもあります。
集合住宅に住んでいる場合はその影響は更に大きくなります。
大きなアンテナを立てていると目立ちます。電波を発信している、というだけで実際には関係なくても
電波障害を受けているのではないか、と受け取る人がいるかもしれません。
もし本当に電波障害を起こしている場合はすぐに電波の発信を停止して原因をつきとめ、
対処をしてからでないと無線(発信)を再開できません。
安全性
特に集合住宅ではアンテナ設置が問題にされるようです。アンテナをしっかり固定していても落下の危険は否定できません。
いくら安全性を説明しても無線をしていない人にとっては理解できません。
無線は非常災害時に役に立つ、と思っているのは無線をしている人の側の考えで、
一般社会の中ではそれ程深刻には受け取ってもらえません。
「いざという時のため」よりは「普段の安全性」が優先されるのが一般社会の常識です。
近隣とのトラブルを避けるためには「無理はしない」がベストです。
確実な方法でできるだけ目立たないように、弱い電波で無線を利用する方が安全です。
近隣とのトラブルで困ったらこれも先輩に相談するべきです。
無線関連の情報
アマチュア無線に関する情報はインターネット上に沢山ありますから、普段から目を通しておくことが必要です。
無線の団体として
日本アマチュア無線連盟(JARL:ジャール)http://www.jarl.or.jp/index.html
があります。サイトのページにはアマチュア無線に関する色々な情報が掲載されています。
内容は資格を取得した人向けで初心者には難しいことが多いかも知れません。
入会金と年会費を払って会員になれば更に情報を得られます。
しかし、無線をしている人全てがこの連盟に加盟している訳ではありません。
加盟しなくても何も問題はありません。
QSLカード(交信証)の交換をJARL経由で希望されたら「ノーカードでお願いします」と言えばそれで済みます。
また、専門誌としてCQ出版社からCQhamradio(シーキュー・ハムラジオ)という雑誌が毎月販売されています。
近くの書店にない場合はネット販売もしています。無線関連の書籍も出版しています。
アマチュア無線4級は2日間の講習会に出て試験に合格すれば殆どの人が合格できるようになっています。
しかし、実際の無線運用には更なる知識と技術が必要です。
資格はあくまで最低ラインの基準をパスしただけ、という意味です。
無線を始めるとその奥の深さを知ります。だからこそ何十年も続けている人がいます。
非常災害時だけの無線利用
元々、非常災害時に無線を利用できればいいだけ。それ以上の知識や技術はいらない、
と思う方がいるかもしれません。
しかし、いざという時にスムーズに交信ができるためには、普段から交信に慣れている必要があります。
一般的な趣味としての無線の楽しみ方は不要でも、最低限の交信の仕方は身につけておくべきです。
また、そのための無線設備(アンテナや無線機など)の維持・管理にはそれなりの知識・技術が必要です。
144Mhzのハンディ機だけで交信する場合は、
無線設備といっても無線機とバッテリーと取り付けるアンテナだけですからそれ程の問題はないかもしれません。
実際に144Mhzで交信をしてみたら「やはり物足りない、もっと遠距離の交信がしてみたい」と思うかもしれません。
自分の住んでいる環境で、どういった無線設備であれば非常時に役に立つのか、
を考えてあれこれ模索するかもしれません。
実際に無線交信をして分かることが沢山あります。
色々な交信を経験して、色々な無線設備を体験して、それらが非常災害時の通信に役立てられれば、と思います。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
非常災害時の家族間での無線交信の検討 私の場合
妻と私の二人が無線交信するにはどうしたら良いか。普段の行動範囲と無線設備を考えてみます。
こうしたらどうか、という内容で実際には一部しかまだ試していません。
現在自宅で使用している無線機はバーデックスFT857DM HF〜144、430Mhzまでのオールバンド機ですが、
設置してあるアンテナの関係で交信できる周波数は 3.5、7、21、50、144、430Mhzになります。
自宅はマンションの10階でアンテナはベランダに設置してあります。
夫婦それぞれの行動範囲は数10km間。この間で交信できる周波数帯と無線機にはどんなものがあるか。
電波の到達距離と実用性
まず7Mhzを利用する場合を考えてみます。
7Mhz、10Wで交信できる範囲は前述のように日本国内や海外とも交信可能です。
7Mhzは電波の波長が長く、電波は空の上の電離層で反射して地面や海面で反射して、を繰り返して伝わります。
空の上の電離層は季節や時間によって状態が変化するので、 電波の伝わる範囲と時間帯が変化します。
5月頃から秋の初め頃までの季節なら、日の出後の朝から夜8時頃までは交信できます。
非常災害時の交信範囲は数10kmで考えてみます。
夫婦のどちらかが自宅、もう片方が外出中場合。
外出している片方が自宅から数10kmの場所で、車にアンテナをつけて広い場所にいれば、
7Mhzを使って自宅との交信が可能です。7Mhzを使えば日常の行動範囲は大体カバーできます。
※ただし、近すぎると直接波が届かない場所では交信できません。
無線機から発信された電波が反射波となって届くには距離があります。
上の図では、アンテナから一つ目の反射波が地面に届くまでの間。この間を不感地帯といい、反射波は送受信できません。
7Mhzで交信するためには固定用或いはモービル用無線機が必要です。携帯用ハンディ機は販売されていません。
今自宅で使っている無線機(オールバンドモービル用無線機)は値段が1台8万円近くします。
私の車、妻の車それぞれにこの無線機を設置するのは現実には厳しい。
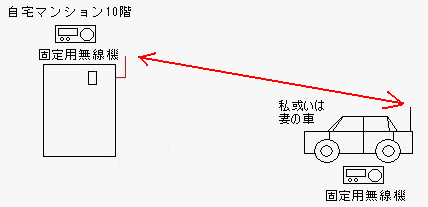
固定用或いはモービル用無線機で7Mhzだけを利用できるものは販売されていないようです。
もしあったとしても車の外への持ち運びには適していません。
たまには電車に乗っての外出もあります。いつも車のそばにいるとは限りません。
また、季節や時間によって交信ができたりできなかったりするのでは、非常災害時の通信には不向きです。
3.5MHzは夜間から明け方まで交信ができますが、この無線機でも車の外に携帯できません。
そこで、144Mhz、5Wの携帯型無線機(ハンディ機)を使ったらどうか。
各メーカーから色々な機種が発売されていますが、手に持つだけでなく、車でも使えるという条件で選択すると
例えばALINCOのDJS17。
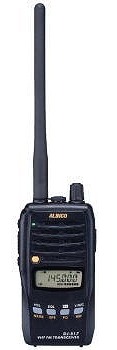
メーカーサイトはhttp://www.alinco.co.jp/denshi/03/djs17.html
ハンディ機の大きさは携帯電話よりちょっと大きい程度です。 これは1台20000円位で買えます。
無線機本体の他に、
ハンディ機に車のアンテナ線を接続するコネクター、車のバッテリーを利用するためのアダプター、
運転中でも交信ができるスピーカ付きマイク、などを入れると合計25000円程度になります。
私の車にはアンテナがありますが妻の車にはないので、そのアンテナ代にプラス数千円かかります。
また、ハンディ機付属のアンテナとは別に、電波をより遠くに飛ばすための高利得のアンテナがあればこれも必要です。
電波出力が5Wと小さくなっているのは消費電力とバッテリーの関係です。
10Wで送信すればバッテリーはすぐなくなります。 付属のバッテリーを使って5Wで送信して4〜7時間持ちます。
車のバッテリーを電源にして使えばもっと長時間交信できます。
この携帯型無線機を夫婦それぞれが1台ずつ持ち歩きます。 2台で約50000円になります。
片方が自宅、片方が外出中の場合、
自宅では、モービル用無線機でも携帯型無線機(ハンディ機)でも、ベランダのアンテナがつながった無線機を使える状態なら、
外出中のもう片方が5Wの携帯型無線機で交信ができるのではないか。 (3.5Km間 確認済み 後述)
144Mhzの周波数は直線性が高いので、電離層は突き抜けてしまいます。主に無線機同士で直接電波をやりとりします。
短所は、山や建物などの障害物があると反射して到達距離が短くなります。
長所は、主に無線機同士で直接電波をやりとりするので、季節や時間帯に関係なくいつでも交信ができます。
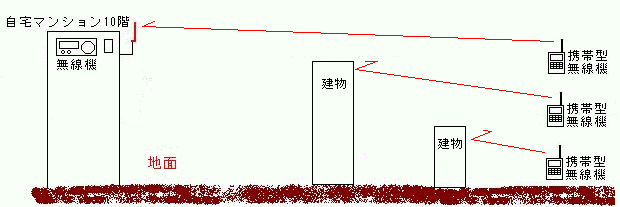
障害物があると反射してその先に電波が届かなくなりますが、
上から見ると、建物に反射した電波が自宅に向かう可能性もあります。
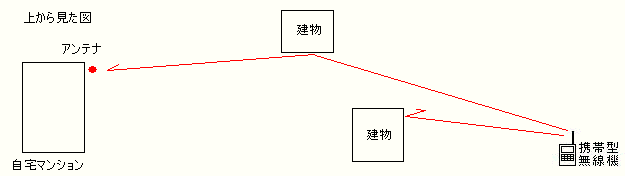
そして両方が外出先の場合、 携帯型無線機(ハンディ機)同士で交信することになります。
携帯型無線機(ハンディ機)に付属しているアンテナを使って、市街地でどの程度の交信ができるのかはわかりません。
夫婦それぞれ外出には車を使うことが多いので、
車にアンテナを設置していれば無線機付属のアンテナよりは電波が飛びます。
交信距離が付属アンテナでどの程度か、高利得アンテナでどうか、車のアンテナでどの程度か、 なども確認する必要があります。
ここまでの話を理解できた方の中には、
「非常災害時の無線連絡は、7Mhzの無線機同士を使い、7Mhzで交信できる時間帯でなければ使い物にならないじゃないか」
と思われるかもしれません。
→7Mhz専用の無線機はモービル機、ハンディ機ともに販売されていません。
HF〜50Mhzなど複数のバンドが利用できる無線機はありますが、
無線機自体が重く、電源は12V(ボルト)なので通常は車のバッテリーを使用します。
車で使うには問題ありませんが、持ち歩きはできません。
山や広場、河川敷などへ出かけて移動運用できるように携帯用のバッテリーもありますが、
普段の生活の中で携帯する無線機ではありません。
また「7Mhzの携帯型無線機を使えば簡単でしょ」と思われるかもしれません。
→7Mhzの携帯型無線機(ハンディ機)は製品としてありません。 昔はあったようですが現在はありません。
7Mhzの電波は波長が長い(半分でも20m)ので短いアンテナ(短縮アンテナ)にすることが難しいからなのか何なのか、
詳しくは分かりません。現在市販されているハンディ機の周波数は50、144、430、1200Mhzで、主流は144と430のようです。
これらは波長が短いので市街地では建物などの障害物で電波が反射して到達距離が短くなります。
この2つの内、144の方が直線性が低いので、430Mhzよりは電波が遠くに飛びます。
従ってハンディ機で数10km間で交信するには144Mhzを使う、ということになります。
144Mhz・5Wの無線機であっても、
電波障害を避けて広い場所、高い場所に移動したり、車のアンテナを利用して交信すれば何とかなるのではないか。
無線機の種類
今回無線機の種類を色々調べてみて分かったのですが、
7Mhzが使えるHFだけのモービル無線機が販売されていません。
車で使うにはHF〜50Mhzの複数バンドが使える8万円前後の無線機が必要となります。
中古の無線機では7Mhzの拡張バンドに対応していない可能性があるので使うとすれば新品です。
結論
非常災害時にいつでも交信ができるためには、
7Mhzが使えるHF〜50Mhzのモービル無線機を夫婦それぞれの車に常備。それプラス144Mhzのハンディ機をそれぞれが携帯。
車にいる時は7Mhzモービル無線機か144ハンディ機を使い、車から離れている時には144Mhzハンディ機を使って交信。
これが理想なのかもしれません。
モービル無線機8万円×2、車用アンテナ、アンテナケーブル他で1万円、合計約17万円。
144Mhzハンディ機25000円×2で5万円。プラス高利得アンテナが数千円。
可能な限りの非常時通信のためには、合計約22万円かかる、ということになります。
非常災害時の通信のためにこれだけの投資が必要になります。
ここまで揃える必要があるのかどうか。
それよりも、144Mhzのハンディ機2台だけ、予算は5万円プラス数千円というのが適当な所ではないか。
とりあえずは144Mhzのハンディ機を1台購入して
アンテナや交信環境など色々な条件で試してみる必要があります。
実際の交信可能距離の確認内容
自宅のモービル無線機 ⇔ 144Mhzのハンディ機、 自宅のモービル無線機 ⇔ 144Mhzのハンディ機+車のアンテナ
ハンディ機 ⇔ ハンディ機 ハンディ機+車のアンテナ ⇔ ハンディ機+車のアンテナ
それぞれの交信可能距離がどの程度か実際にやってみて結果が分かったら追加掲載する予定です。
以上のように、市街地で144Mhz・5Wの交信距離がどの程度なのかは実際に試してみないと分かりません。
しかし、災害時には携帯電話は確実に使えません。
では他にどんな通信手段があるか、と言えば何もありません。 無線以外に通信手段がないのが現実です。
無線がなければ携帯電話がつながるまで不安で不便な時間を何時間も過ごすことになります。
また、何もないよりはお守り代わりであっても安心につながります。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
交信実験 23.8.25追加
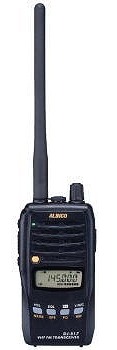 |
使用無線機:ALINCO DJS17 144Mhz 5W FMモード 2台 駅前:無線機にDIAMOND SRH779 ロッドアンテナ(全長44cm)を接続。 ジャスコの2階外の喫煙所。駅のロータリーが見え、自宅方向の背中側にジャスコの7階建てビル。 目の前右手に高層マンション。自宅方行には他にいくつかビルがある。 自宅:マンション10階のベランダに設置してある DIAMOND VX1000 アンテナと無線機を接続。 距離:直線で約3.5Km |
| 交信結果 自宅→駅前 シグナルレポートは59.問題なくはっきり聞こえる。 駅前→自宅 スケルチ解除でかろうじて聴取。会話は成立。 |

23.8.28追加
車で移動しながらハンディ無線機で交信。車用アンテナ(DIAMOND MR73S)を使用。自宅アンテナは上記と同様。
下図の赤線上を移動。交信結果は良好。自宅→ハンディ機、ハンディ機→自宅、ともに59.
駐輪場でロッドアンテナに変更するが、交信結果は良好。

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
非常災害時の個人的な通信方法 144Mhz帯の場合
普段から使用する周波数を決めておいて、相手のコールサインを呼び出す。
或いは、呼び出し周波数で呼び出す、のどちらかになります。
具体的には、
144Mhz帯では、電話(通話)で使用できる周波数は
モードがUSBなら144.10〜144.50Mhz。モードがFMなら144.60〜145.65Mhzまでの間。
呼び出し周波数は145.0Mhzなのでこれを避けて、普段から他の人が交信していない周波数を探します。
例えば145.5Mhzに決めておきます。
自宅に固定無線機を設置している場合でもハンディ機でも同様です。
災害発生時に電源を入れて決めておいた周波数145.5Mhzに合わせます。
自分から相手のコールサインを呼び出したり、相手から自分のコールサインを呼びかけられたら応答して交信します。
もしこの周波数を他者が利用していた場合は、呼び出し周波数を利用する、と決めておきます。
外出中でも交信ができるようにハンディ機を用意しておくと便利です。
非常災害時のための備え
災害時はまず携帯電話で連絡し、それで通じなければ無線で呼び続けることになります。
いざという時に迷わないように、普段から交信の練習をしておく必要があります。
また、普段から外出中のどの場所から自宅の間ではどの程度の交信ができるか、
お互いが外出中の場合、行動範囲のどこからどこの間ならどの程度の交信ができるか、
などの実験をしておく必要があります。
電源の確保(停電対策)
ハンディ機はバッテリー電源ですから、バッテリーが残っている内は使えます。
しかし固定用無線機は家庭用コンセントに差し込んだ安定化電源を使用します。停電になったらコンセントは使えません。
そこで、車の12Vバッテリーを非常用電源として用意しておきます。
過充電防止装置のついた充電器をコンセントに差し込んでおいて、日常的に充電しておきます。
停電になったらバッテリーから無線機に直接12Vの電源をつないで固定用無線機を使用します。
ハンディ機も車用の電源が使えるアダプターがあればそれを使えばこのやり方で使用できます。
バッテリーは開放式、密閉式の2種類があり、開放式では水素ガスが発生します。
これは火花などで引火して危険です。また開放式・密閉式共にバッテリー液は希硫酸です。
バッテリーを室内に保管するのは危険なので、家の外、集合住宅等ではベランダに保管します。
雨水が当たらないように防水処理と、換気と熱の発散を考慮した保管方法を考えます。
また、いざという時に使えるように、定期的にバッテリーを電源に使って無線機が使えるかを確認する必要があります。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
災害時の色々なケース
固定電話や携帯電話が使えない状況で、家族や知り合い間で連絡する場合にはどんなケースがあるか。
お互いが自宅にいる場合、片方が自宅・片方が外出中、両方が外出中、の3つについて考えてみます。
※予算は考えずに交信ができることを優先にした場合です。
1.お互いが自宅にいる場合
同居の家族以外の家族や知り合いとの連絡に無線を利用します。当然相手も無線の資格を必要とします。
携帯電話が不通でも無線は設備(アンテナと無線機等)と電源さえ確保できていれば利用できます。
遠距離ならHF帯7Mhz、季節や時間によって7Mhzが利用できない場合は3.5Mhzも利用できます。
近県間や近距離なら144Mhzで季節・時間に関係なく利用できます。
また、地震や洪水・火災などで地域が孤立した場合、外への救援要請などに自宅の無線が利用できます。
地域の防災対策本部との無線連絡方法について普段から打ち合わせをしておく必要があります。
地域の無線クラブがあればそうした団体が窓口になっている場合があります。
2.片方が自宅・片方が外出中
長距離通信ならHF帯7Mhz、近距離なら144Mhz帯の無線機を利用します。
車で外出することが多ければ車専用のHF無線機を設置しておくか、144Mhz携帯型無線機(ハンディ機)を持ち歩きます。
車でHF7Mhzで自宅と交信する場合、季節や時間によって交信が不可能な状況も生じます。
その場合は季節や時間に関係ない144Mhzのハンディ機に車のアンテナを接続して交信します。
市街地にいる場合は電波障害は避けられませんが、できるだけ障害を避けられる場所に車で移動してから交信します。
車から離れている場合には144Mhzのハンディ機しか手元にありません。
144Mhzは市街地では電波障害で通信距離が短くなりますが、付属のアンテナではなく高利得のアンテナを使用したり、
広い場所、高い場所に移動するなど、電波出力を最大限に利用できる環境を整えれば
自宅にいる家族と交信できる可能性があります。
東日本大震災の場合、地震発生直後に携帯電話は当然不通になりました。
また電車が止まったり道路が渋滞して帰宅できない人が沢山いました。
地震発生から時間が経って携帯電話が利用できるようになっても
こうした時に、例えば駅など多くの人が集中する場所で携帯電話を一斉に使用すると、
近くの中継局がさばききれなくなって電話はまた不通になります。
そうした場合144Mhzのハンディ機があれば、電波障害を避けた環境に移動して自宅と交信できる可能性があります。
3.両方が外出中
車で外出することが多ければ車専用のHF7Mhz無線機を設置しておくか、144Mhz携帯型無線機(ハンディ機)を持ち歩きます。
車であればHF7Mhzで外出中のお互い同士で交信できます。しかし季節や時間によって交信が不可能な状況も生じます。
その場合は季節や時間に関係ない144Mhzのハンディ機に車のアンテナを接続して交信します。
お互いに、或いは片方が車から離れている場合には144Mhzのハンディ機しか手元にありません。
144Mhzは市街地では電波障害で通信距離が短くなりますが、付属のアンテナではなく高利得のアンテナを使用したり、
広い場所、高い場所に移動するなど、電波出力を最大限に利用できる環境を整えれば
外出中の家族と交信できる可能性があります。
外出中同士の間では交信ができなくても、自宅と交信できれば自宅が中継基地の代わりになって情報を伝えられます。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
おわりに
非常災害時に家族や知り合いと無線で連絡をするにはどうしたら良いか。
思いつく範囲でまとめてみました。
初めは「無線免許の取得方法」と「私の場合の、非常災害時だけの無線利用の仕方」だけで済む、
と簡単に考えていましたがそうはいきませんでした。
あれもこれも、と加えていったら膨大になりました。これでもまだ足りません。
無線の楽しみ方は色々あり、デジタル無線機とパソコンをつないで文字のやり取りをすることもできます。
専用の機能が付いた無線機を使ってこれを利用すると、相手を呼び出すことが可能になるようです。
しかし、私はやったことがないので説明のしようがありません。
私が利用しているのは一般的なアナログ無線機で、シンプルな機能しかありません。
この解説は、無線の初心者が実行しやすく、予算もそれ程かからない程度の簡単な装備でできる範囲でまとめてみましたが.
無線を長年楽しんでいるベテランの方なら、また違った非常時通信の方法を考えられるのかもしれません。
今回は実際の交信実験ができていない状態でまとめてみました。
大災害の後で、「とにかくこうした方法もある」と解説することを急いだ結果です。
144Mhzの交信範囲など追加情報がまとまったら更新する予定です。
また、非常災害時の無線通信の利用について、新しい情報を得たり他の方法を思いついたりしたら補足・更新する予定です。
23.5月
※アンテナ調整についてアドバイスをいただき、内容を一部変更しました。ありがとうございました。
30.1.15