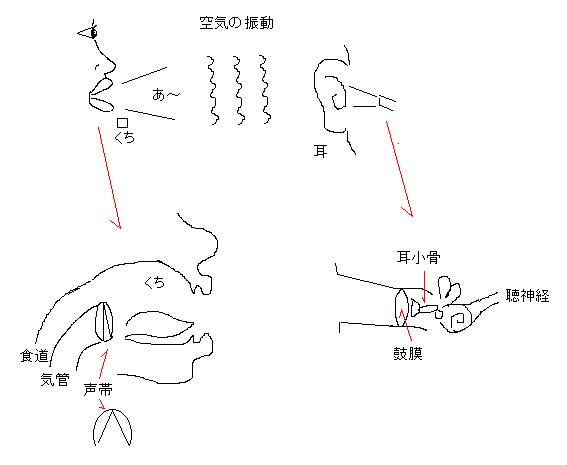
ステレオとモノラル (20.7.4)(最終更新:24.9.17)
はじめに
音楽の流し方を解説していると、ステレオとモノラル、という言葉を良く使います。
これがどういう意味なのかを知っていると話が早いので、解説してみました。
簡単に分かってもらうことを目的にしているので、
正確さには欠ける部分もあります。
「大体こんなものだ」という理解ができればいいかな、という内容です。
詳しく知りたい方は自分でインターネット上を検索してみてください。
音の伝わり方
声(音)は空気を振動させて波となり、波が空気中を伝わる。
人が二人いて、片方の人が「あ〜〜」と声を出すと、もう片方の人に「あ〜〜」と聞こえる。
これを詳しく説明すると、
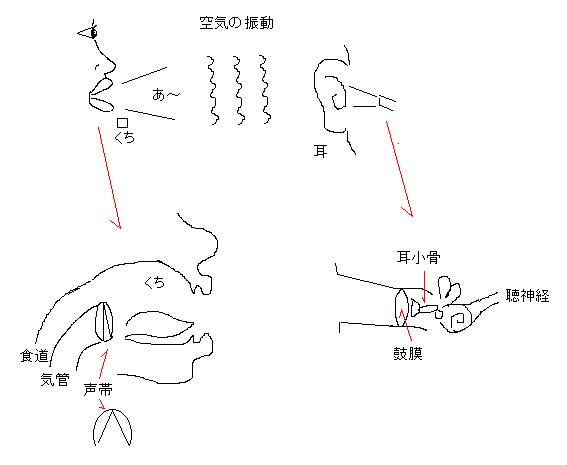
声を出す人の気管から空気の流れが出て、それが声帯を震わせて声(音)になる。
声(音)は波の振動となって空気中を伝わり、聞く側の人の耳の鼓膜を振動させる。
これが声(音)の伝わり方。
声を出す人、聞く人の二人の距離が離れて行くと、いずれは声(音)が聞こえなくなる。
これは空気の振動の波が減衰して行くからで、
到達する距離は声(音)の大きさに比例する。
離れていても人の声を聴くことができないか。
そうやって考えられたのが、
声(空気の振動)を電気の信号に変え、再び声(空気の振動)に戻す回路。
電磁誘導
電気を流すことのできるコード(線)を導線という。
導線同士が触れても電気が流れないように、導線の表面に絶縁物質を塗装する。
(例えばエナメル線など)それをクルクル巻いてトンネルを作る(=コイル)。
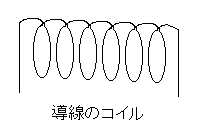
コイルの中に磁石を入れて動かすと、コイルの両端AとBには小さい電気が流れる。
これを電磁誘導という。(磁石とコイルの位置が変わると、コイルに電気が流れる)

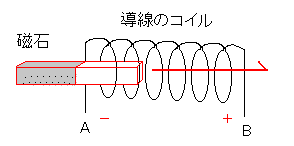
磁石の動きで流れる電気の向きが逆になり、
AとBそれぞれには、プラスの電気が流れたりマイナスの電気が流れる。(交流)
※実際には磁石の極性とコイルの方向によって、流れる電気の向きが決まっていますが、ここでは省略。
磁石を固定して、コイルを移動しても同様にAとBには電気が流れる。
磁石とコイルの位置関係が変化することで電気を流すことができるのが電磁誘導。
逆に、磁石やコイルを動かさない状態でAとBに電流を流す。
すると、トンネル内に磁力が発生して、磁石を動かすことができる。
(コイルに電気が流れると、磁石とコイルの位置が変わる)
交流と直流
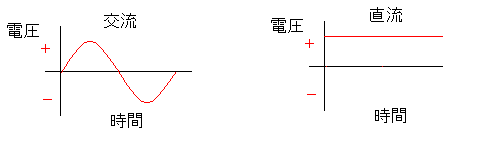
交流はプラスの極とマイナスの極を行ったり来たりする。電圧も変化する。
家庭のコンセントは交流電圧 約100ボルト。
直流は極性が一定、電圧も一定。乾電池は1.5ボルトの直流。
テレビ、ビデオデッキ、パソコンなど、音や映像を扱う家電品の多くは、
電源コードをコンセントにつなぐ。コンセントの交流100ボルトを、
12ボルトや6ボルトなどに下げて、直流にして電気回路に使っている。
スピーカーの構造
丸い紙の中心をへこます。横からみると下図2.
へこみの後ろ側にコイルを貼り付けて固定(図3)。
コイルの中に磁石を入れて(図4)、コイルの壁に触れないように支えて固定(図5)。
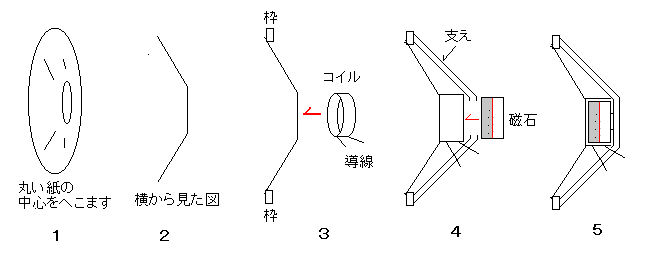
これがスピーカーの構造。
スピーカーとマイクは原理が同じなので、
分かりやすいように、マイクの原理を先に説明すると、
(下図)空気の振動が丸い紙に伝わると、へこみの裏にあるコイルが動く。
するとコイルと磁石の位置が変わって、コイルに電気が流れる。これがマイクの原理。
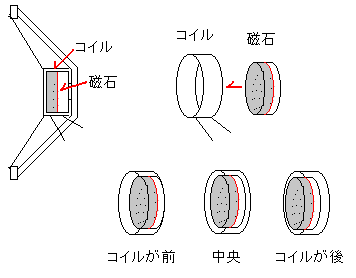
逆に、コイルに電気信号を流すと、
コイルと磁石の位置が変わり、コイルが動いて紙が振動する。
この振動が空気中に伝わって音を出す。これがスピーカー。
増幅回路(アンプ)
マイクで発生した電気信号は小さいので、
そのままスピーカーのコイルに流しても音を発生させることができない。
そこで増幅回路を使う。
電気信号を大きくするための回路を増幅回路(アンプ=増幅器)という。
増幅回路の中では、交流を直流に変えて電気の流れを一定にしている。
下図の左側のスピーカー1に向かって「あ〜」と声を出すと、
増幅回路で電気信号が大きくされて、スピーカー2から大きな「あ〜」という音が出る。
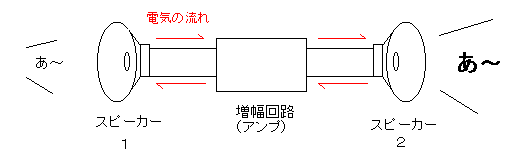
この時の電気信号の流れを説明すると、
スピーカー1では紙が動いてコイルに電気信号が流れ、
増幅された信号がスピーカー2のコイルに流れる。
スピーカー2ではコイルに流れた電気信号でコイルが動き、丸い紙を振動させる。
こうして人の耳に音が聞こえる。
スピーカー1は音を受け取るだけの機能があればいいので、
スピーカーの構造を小さくできる。そうして小さくなったものがマイク。

スピーカーは、「電気信号を空気の振動に変える」
マイクは、「空気の振動を電気信号に変える」。
どちらも原理は同じ。
音の位置
マイクが一つということは、音の出所(音源)が一つ。
マイクからの電気の通り道も一つ。+から出て、−に帰って来る。
通り道が一つをモノラルと言う。モノレールは、モノラルのレール。
一般的に、音源が一つの場合をモノラルと言う。
下図はマイクを一つ使った場合。
A:左から汽車が近づいてきて、B:正面にきて、C:右に遠ざかる。
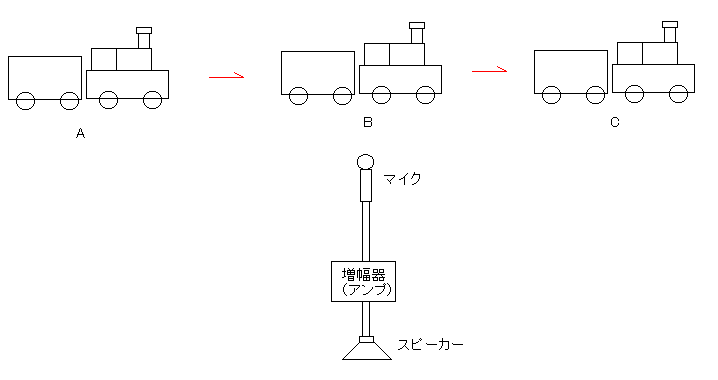
汽車の音を直接聞けない位に離れた位置にいる人がスピーカーの音を聞くと、
汽車の音は、小さく聞こえ、大きく聞こえ、また小さく聞こえる。
つまり音の大小だけ。
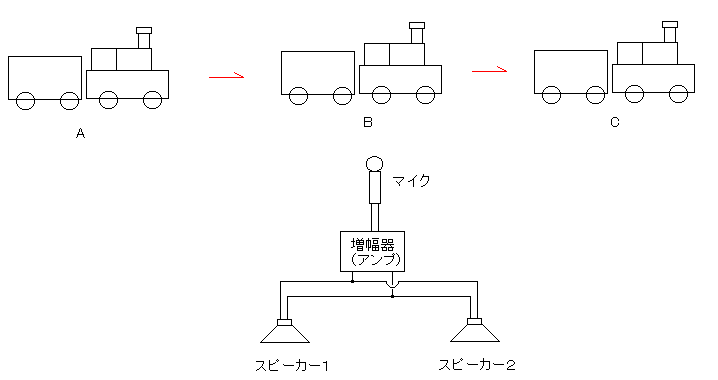
スピーカーを2つにしても、それぞれのスピーカーからは同じ音が出ているので、
音の大小の変化だけ。
下図はマイク、増幅器、スピーカーを二つ使用した場合。
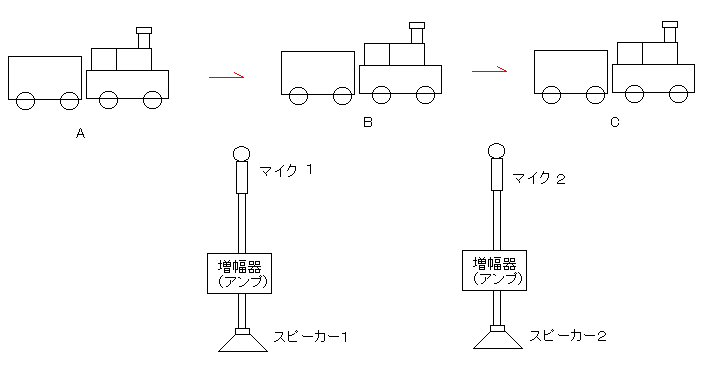
スピーカー1の音とスピーカー2の音を同時に聞くと、
汽車の音は左から聞こえて正面にきて、右に遠ざかっていく。
この場合、音の大小に加えて、音の位置を感じることができる。
マイクが二つ=音源が二つ。電気信号の流れが二つ。
これをステレオと言う。
人間の耳は左右に一つずつあり、
音源を左右から感じることで音の方向、距離を感じている。
マイク(音源)が2つ=ステレオ=その場で音を聞く状態(臨場感)
ステレオ音源は臨場感を与える。
音楽の場合を例にすると、下図のようになる。
マイク1からピアノ、マイク2からギター、両方からボーカルの声が入るとすると、
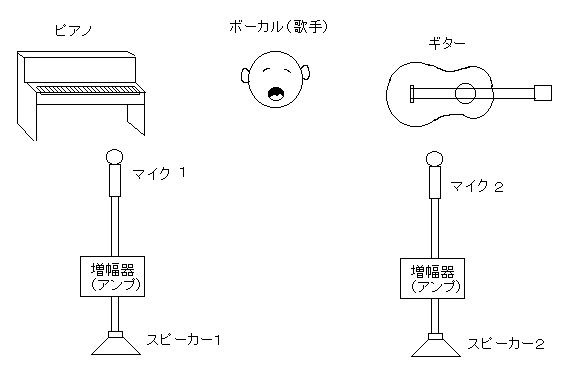
スピーカー1、スピーカー2を同時に聞くと、
ピアノ、ギター、ボーカルの位置関係そのままの音が聞こえる。
ライブコンサートやオーケストラ演奏などを大きな会場で聞く場合がこれ。
実際には、マイクは各楽器や歌い手それぞれにあり、
各音をミキサーという機械で混ぜて増幅器につなぎ、スピーカーは二つという構成になる。
電気の流れの簡略化
2つのマイクから信号が出て(ステレオ音源)、
それぞれの増幅器に入り(ステレオ増幅器)、
2つのスピーカーがつながっているとする。
ステレオ増幅器と2つのスピーカー部分だけを取り上げてみると、
1:それぞれのスピーカーにプラスからマイナスに電気が流れている。
2:スピーカー2のプラスとマイナスの位置を逆にする。
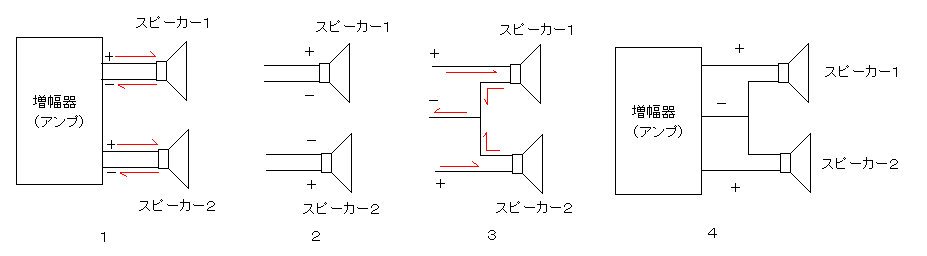
3:マイナスを共有して1本にする。
4:増幅器とつなぐ
4の回路と1の回路は同じ電気の流れになる。
スピーカー1とスピーカー2を、ステレオヘッドホンの左右だとすると、
コードは3本で左右のヘッドホンを鳴らすことができる。
ステレオヘッドホンのコードの先の金具(プラグ)をみると、
金属が3つに区切られている。
わかりやすく、赤、青、緑で色分けしてみると、
3つの金属部分からそれぞれコードがつながっていて、マイナスは共有になっている。

これがステレオヘッドホンのプラグの構造。
※プラグとジャック
差し込む金具(オス)をプラグ、差し込まれる金具(メス)をジャック(端子)という。
モノラルとステレオの使い分け
ただ音だけが必要な場合はモノラルの音。臨場感が必要な場合はステレオの音。
モノラルの例:電話、インターホン、ボイスチャットなどの音
ステレオの例:音楽、ドラマ、映画などの音
電話はしゃべる人が一人なので音源は一つ。
声が聞こえるかどうかが問題で、音の位置は関係ない。だからモノラルで足りる。
yahooのボイスチャットや、スカイプ、msnメッセンジャーなども声が聞こえればいいので、
モノラルの音の流れを扱っている。
チャットの音の流れ
yahooチャットの場合で説明すると、
チャット部屋に入室し、ボイスが有効になると、
チャットサーバー内のボイスサーバーに接続される。
この時、パソコン(PC)はマイクからの音をチャット部屋に流すように、
マイク、CD、外部入力などのPCに入る音の中からマイクを選択する。
マイクはモノラルの音をPCに入力する。チャットのボイスサーバーもモノラルの音を扱う。
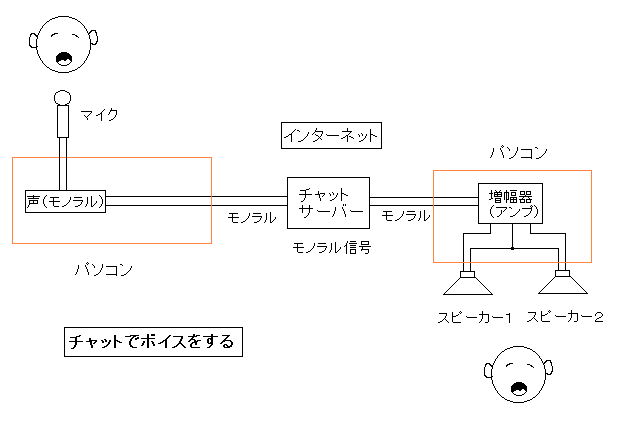
聞く側も
yahooチャットサーバーからモノラルの音を受け取って、スピーカーから聞いている。
ボイスチャットで音楽を流す場合、
押しっぱなしツールなどを使って話すボタンをロック。
ソース指定でステレオミキサーなどを選択して音楽を再生すると、
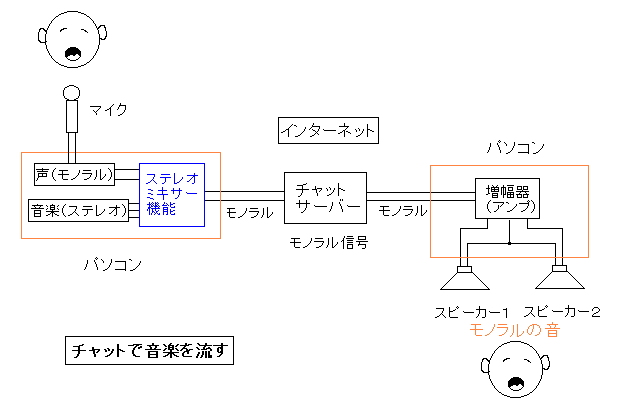
マイクからのモノラルの音と、音楽ファイルからのステレオの音が、
ステレオミキサー機能によって一緒になって、モノラルの音となって、
チャット部屋に流れる。
流す人のパソコンではステレオ音源で音楽が鳴っていても、
チャットで扱う音はモノラルなので、
チャット部屋で聞く側の人のパソコンではモノラルの音として聞こえる。
聞く側の人のパソコンではスピーカーが2つあっても、
チャットの音源が一つ(モノラル音源)なので、
2つのスピーカーから同じ音が出ている状態。
これに対して、俗に高音質と言われるjetcastやエンコーダなどの配信ソフトは、
音源をステレオで扱う。
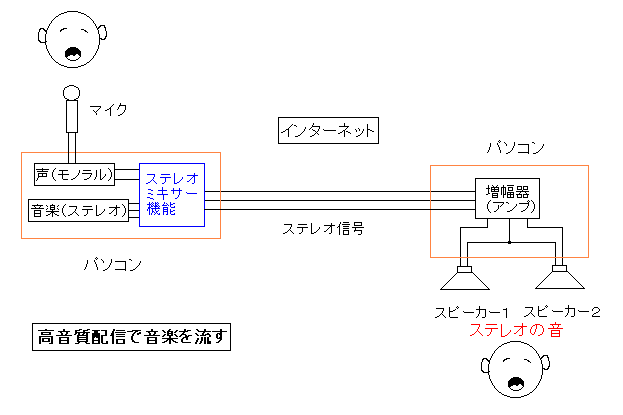
中継サーバーがない直接配信なので、ステレオ録音された音楽を流していれば、
聞く人のパソコンでもステレオで聞くことができる。
音楽と一緒にマイクでしゃべると、マイクからの音はモノラルなので、
音楽はステレオで流れ(スピーカ1と2では別々の音)、
おしゃべりはモノラルで聞こえる(スピーカー1と2と両方から同じ音)。
マイクの種類
マイクにはスピーカーと同じ原理のダイナミックマイクと、
もう一つ、コンデンサーマイクがある。
ダイナミックマイク
カラオケで使うような手に持つマイクが一般的。
これは音の通り道が一つのモノラル。
マイクプラグは金属が二つに区切られている。プラスとマイナスの2つの電極がある。
カラオケマイクのプラグはモノラル標準プラグ。
これをパソコンのマイク端子に接続するには、
モノラル標準プラグをモノラルミニプラグに変換するプラグを使用。
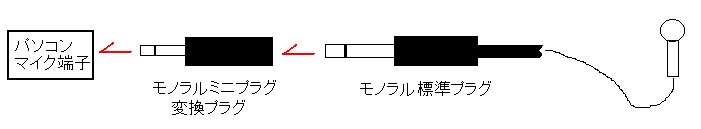
コンデンサーマイク
コンデンサーは電気を蓄えておく小さな部品。
薄い金属の板が2枚あって、その間に電気を通さないもの(絶縁体)を入れる。
2枚の金属板に一定の電圧をかけておいて空気の振動を加えると、
金属板の距離が変化するので、電圧に変化が起きる。
これを電気信号として取り出すものがコンデンサーマイクの原理。
音の信号はモノラルでプラスとマイナスだが、
電圧を加えるために、コンデンサーマイクにはもう一つ、電圧端子が必要。
従って、PCのコンデンサーマイクの端子(ジャック)は内部の金属が3つ。
コンデンサーマイクのプラグは金属が3つに分かれていて、
見た目はステレオヘッドホンのプラグと同じ。

ダイナミックマイクは、
コンサートやカラオケスタジオなどで手に持ったり、スタンドに固定して使用する。
音の質(音質)が豊かに取り込める。
コイルと磁石で構成されているので小さくするには限界があり、高価。
コンデンサーマイクは、
小さくできるのでパソコン用のマイク、ヘッドホンマイク、携帯電話のマイクなど
に利用されている。
音質よりは小型化と経済性。ダイナミックマイクより安価。
一般的なパソコンのマイク端子(ジャック)は、ダイナミックマイクとコンデンサーマイクの
両方が使えるようになっている。つまりパソコンのマイク端子(ジャック)には、
音の流れ(プラス、マイナス)の2つに加えて、
コンデンサーマイク用の電源電圧が取り出せるように3つ目の電気の流れがある。
※ダイナミックマイクが使えないパソコンもあります。
音の記録、入れ物
音を記録する機械として世の中に最初に登場したのはオルゴール。
その後がレコード。
レコードは、音の振動を針で円盤状のプラスチック板に刻んで記録(録音)。
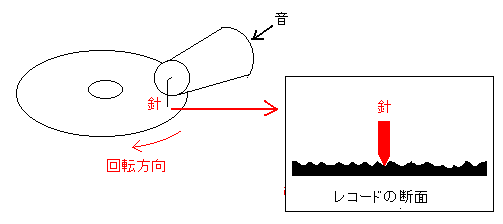
音を再生する機械は蓄音機と呼ばれた。
これは円盤に針を乗せて円盤を回転させるもの。
ビクターのロゴマークで、犬がラッパに耳を傾けている。あれが蓄音機。
円盤(レコード板)に刻まれた山と谷を針がこすることで音を拾い、
当初はラッパをつけて音を大きくした。
音はモノラル。
その後、円盤を電気で回し、音を大きくするために電気による増幅器が使われ、
電気蓄音機(電蓄)と呼ばれた。
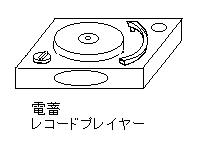
その後、電蓄が進化してステレオ音源で録音と再生ができるようになった。
市販された機械は再生専用。
昭和40年(1960年)代には「ステレオ」が商品名になり、レコードが社会に浸透。
音の入れ物はその後テープが登場。
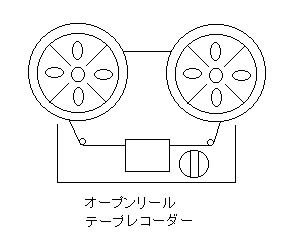
当初はオープンリールのテープレコーダーが開発された。
金属の粉をテープの表面に貼り付けてあり、音の信号を磁化させて記録させる。
テープ表面が磁気ヘッドをこすることで録音、再生ができる仕組み。
オープンリールはテープも機械も大きく、持ち運びが大変だった。
これが小さくなったのがカセットテープレコーダー。
これも最初はモノラルの音を扱っていたが、後にステレオの音も扱い、
ソニーがウォークマンを発売し、持ち運ぶ音楽が浸透。
レコードもテープも、音の波をアナログ信号で記録したもので、アナログ録音と呼ばれる。
音の波は下図のように、山と谷のつながり。
 音の成分は
音の成分は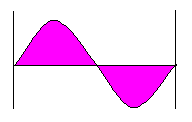 こうなる。
こうなる。
その後登場したCDは、音の波をデジタルの信号で記録したもので、
デジタル録音と呼ばれる。
デジタルとは数値化のこと。
デジタルデータは、信号があるかないかを0と1の数値で表現したもの。
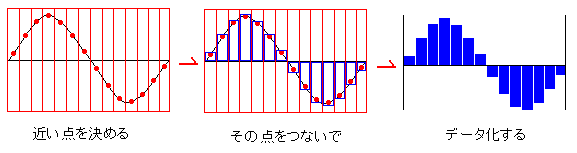
CDの表面に音の記録が刻まれていて、そこに光を当てて、
反射して来る光で信号の内容を読み取る。
レコードやテープはこすって音の信号を取り出すが、
CDはこすっていない。光を当てているだけなので、音の劣化が殆どない。
このデジタル録音が今では主流になっている。
音の入れ物はCDからMDになり、mp3プレイヤーが広まっている。
パソコンに音楽CDを入れて音楽を取り込む(録音する)場合もデジタル録音。
音楽データをデジタルデータとして保存する。
保存の仕方にはmp3やwmaなど、色々な形式がある。
音楽の録音作業
音楽CDを作る場合を考えてみる。
音の配置
ピアノ、ギター、ボーカル、と3つの音を録音する時、
スタジオ内の立ち位置を決めて、2つのマイクで行なうことができる。
しかし、音の大きさで比較すると、ピアノの音が大きく、声は小さい。
3つの音それぞれにマイクをつけて、それぞれの音を単独で扱えた方が便利。
それぞれのマイクからはモノラルの音が取り出せる。
この3つの各音の音量を調整して電気的に合成する機械(ミキサー)を使う。
ただ、音を合成するのはモノラルミキサー。
合成した音の位置を調整できるようにしたものがステレオミキサー。
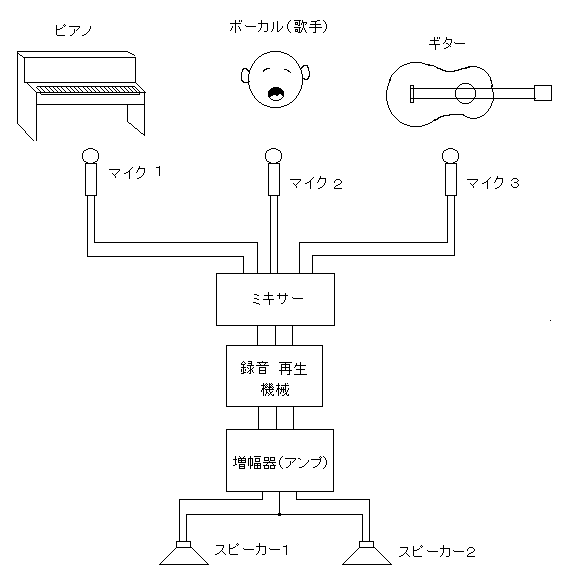
ステレオミキサーで合成された音はステレオの音となり、各音の配置が調整できる。
ミキサーから出た信号を録音機械で録音。
再生機械で再生して、録音された音を確めることができる。
音が良ければそれをカセットテープやCD、MDに録音して完成。
パソコンのステレオ録音と編集ソフト
パソコン(PC)の音の入口はマイク端子が一般的なので、
これを例に録音・編集について説明。
パソコンのマイク端子はモノラル音源を扱う。
例えば、昔、カセットテープにステレオ録音された音楽があるとする。
この信号はステレオアナログ信号。
これをパソコンでステレオ録音するには、そのままではできない。
カセットプレイヤーのヘッドホン端子からはステレオの音が出ていても、
パソコンのマイク端子がモノラルなので、モノラル録音しかできない。
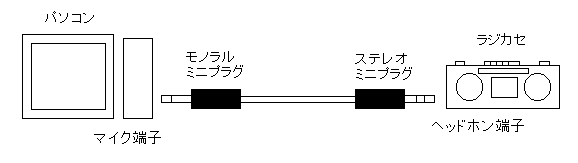
そこで、
カセットテープのステレオアナログ信号を、ステレオデジタル信号に変える機械を使う。
色々な製品があるようですが、ここではその一つを取り上げます。
例)メーカー:CREATIVE クリエーティブ
Sound Blaster Digital Music PX 値段:約10000円 → 24.9月現在 生産されていないらしいです。
同様のものとして、
Sound Blaster Digital Music Premium HD 型番:SB-DM-PHD 定価:8900円 (24.9.17現在)
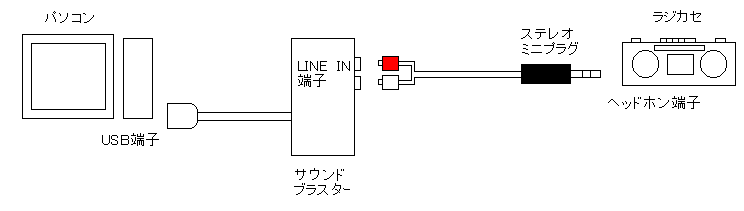
このように接続すると、
カセットテープのアナログ信号をデジタル信号として、PCに取り込むことができる。
サウンドブラスターには録音ソフト、編集ソフトがついている。
録音できる音は、WMA、MP3、WAVそれぞれステレオ、モノラルどちらでも録音できる。
ラインイン端子があるので、レコードプレイヤーとアンプを接続して、
アンプのラインアウトとサウンドブラスターのラインイン端子を接続すれば、
レコードの音をステレオ録音できる。
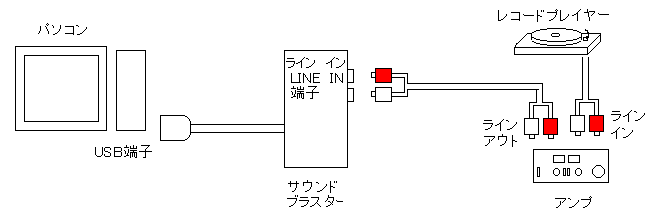
また、マイク端子もあるので、自分の声や楽器演奏の音を録音できる。
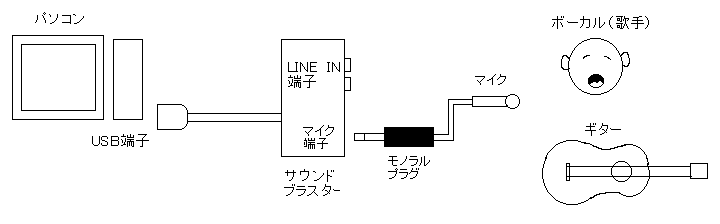
例えば、ギターと歌を録音する場合、まずサイドギターを録音。
それを聞きながら歌を録音。サイドギターを聞きながらリードギターを録音。
この3つの音を編集ソフトで合成して音の位置を調整する。
すると、サイドギターが左から、リードギターが右から、歌が中央から、
という配置でステレオ録音された音楽ファイルができる。
また、最近のテレビはステレオ放送。
例えば音楽ライブの番組を録画。テレビのヘッドホン端子はステレオなので、
サウンドブラスターにラジカセをつなぐのと同様に、テレビのヘッドホン端子に接続。
ビデオを再生して録音すると、ライブの音がデジタルファイルとして保存できる。
ステレオ・モノラル 音の変換
ステレオアナログの音を別の入れ物(パソコンなど)にステレオデジタル録音するには、
サウンドブラスターなどの機材できる。
アナログでもデジタルでも、
ステレオの音をモノラルの音に変換するのは簡単。変換プラグを使うだけ。
しかし、モノラル録音された音をステレオの音に変換するのは簡単にはできない。
モノラルの音は、各音の信号が一つのまとまりとなっているので、
それをバラバラに分ける作業が必要になり、簡単にはできない。
放送
話は最初に戻りますが、離れていても人の声を聴くことができないか。
そうやって考えられたのが、
声(空気の振動)を電気の信号に変え、再び声(空気の振動)に戻す回路。

このマイクの電気信号は増幅されてスピーカーに届く。
増幅回路(アンプ)からスピーカーまでの距離が長くなると電気信号は減衰する。
電気コードには抵抗があり、コードが長くなる程抵抗が大きくなるので、
例えば100m、1km、10kmと離れていけば、
マイク・増幅器からの電気信号はやがてゼロになり、スピーカーは鳴らなくなる。
もっと遠くに離れた人に声を届けることができないか。
そうやって考えられたのが無線。
送信機と受信機
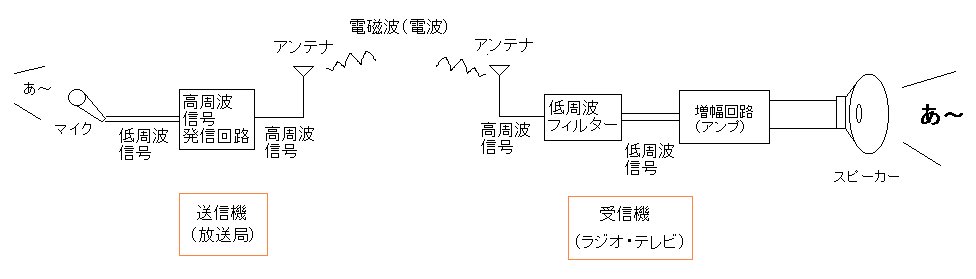
送信機
マイクで生じた電気信号は、低周波信号と呼ばれる。
この信号を高周波信号と一緒にして、発信回路からアンテナへ。
アンテナからは電磁波(電波)となって発射される。
電波は磁力線と起電力の関係で空気中を(空気がなくても)伝わる。
受信機
アンテナから取り込んだ高周波信号から、低周波だけを取り出し(低周波フィルター)、
増幅器で大きな信号にしてスピーカーを鳴らす。
テレビの場合は、映像信号も取り出して映像も映す。
ラジオ・テレビ放送
送信機(放送局)
マイクからの音や音楽、カメラからの映像などの信号を電波に混ぜて送信。
混ぜる信号が音だけのものをラジオ放送。音と映像信号を送信するものがテレビ放送。
受信機(チューナー)
電波をアンテナで受取って、電波から音や映像の信号を取り出して、
増幅器回路(アンプ)で増幅して、スピーカーを鳴らし、映像を映し出す。
音だけを扱うものをラジオ受信機。音と映像を扱うものをテレビ受信機。
電波の種類
AM電波、FM電波、テレビ(VHF、UHF)電波などが一般的。
受信機の名前でいうと、AMラジオ、FMラジオ、テレビ。
放送する音の信号
元々は放送自体がモノラル放送だったので、
受信機で扱う信号もモノラルの音を扱っていた。AMラジオはスピーカーが1つ。
FMラジオはステレオ放送。テレビはモノラル音源の放送だった。
その後テレビはステレオ放送となり、AMラジオもステレオ放送になる。
放送がステレオになると、受信機もステレオ信号を扱うようになった。
現在では、受信機のAMラジオ、FMラジオ、テレビ、それぞれが
ステレオ放送を受信できるものが主流になっている。
音はステレオの音として受信できるので、臨場感のある音を聞くことができる。
受信機と記録装置
ラジオ
ラジオとカセットテープ録音機が一緒になったものがラジカセ。
ラジオとMD録音機が一緒になったものもある。
テレビ
テレビの信号は、音と映像の2つの信号を扱う。
ビデオテープデッキ
音声の信号が元々はモノラルだったので、ビデオデッキの音は当初はモノラル。
テレビがステレオ放送となり、ビデオデッキもステレオ録音ができるようになったのが
Hi-Fi(ハイファイ)デッキ。現在ではステレオ録音ができるものが主流。
ビデオテープは音声・映像共にアナログ信号で記録。
映像やビデオデッキの詳細についてはこちら。
DVD、HDD
その後DVDデッキが登場。これはデジタル信号に変換して記録。
DVDは一度記録したものを書き直しができるもの、できないものがある。
ハードディスク(HDD)とDVDの2つで記録・再生できるものが登場。
これは音と映像信号を一度HDDに記録。編集してからDVDに記録できる。
また、ビデオテープとHDD、DVDの3つの間で記録、再生、編集ができるものも登場。
DVDデッキもHDDデッキも、音はステレオで扱う。
あとがき
ステレオ、モノラルというテーマで解説を書き始めて、なかなか終わりません。
あれも、これもと取り入れていたら切りがなくなりました。
とりあえずここで一区切りとします。
難しい部分はサラっと流してもらって構いません。
私も良く分からなくて、説明が中途半端になっている部分もあります。
不十分な内容ですが、ステレオとモノラルの違いが少しでも分かって頂ければ幸いです。